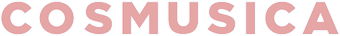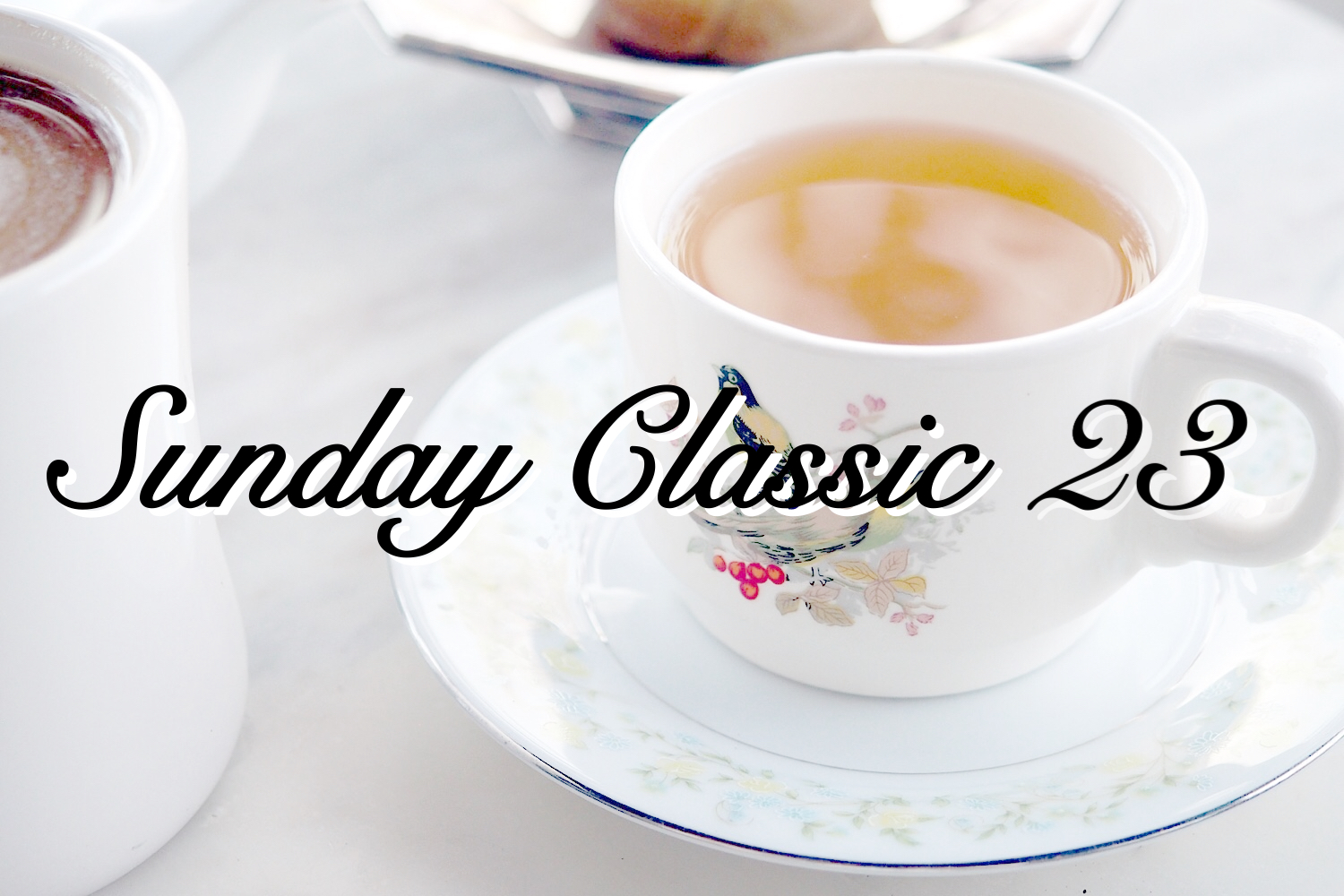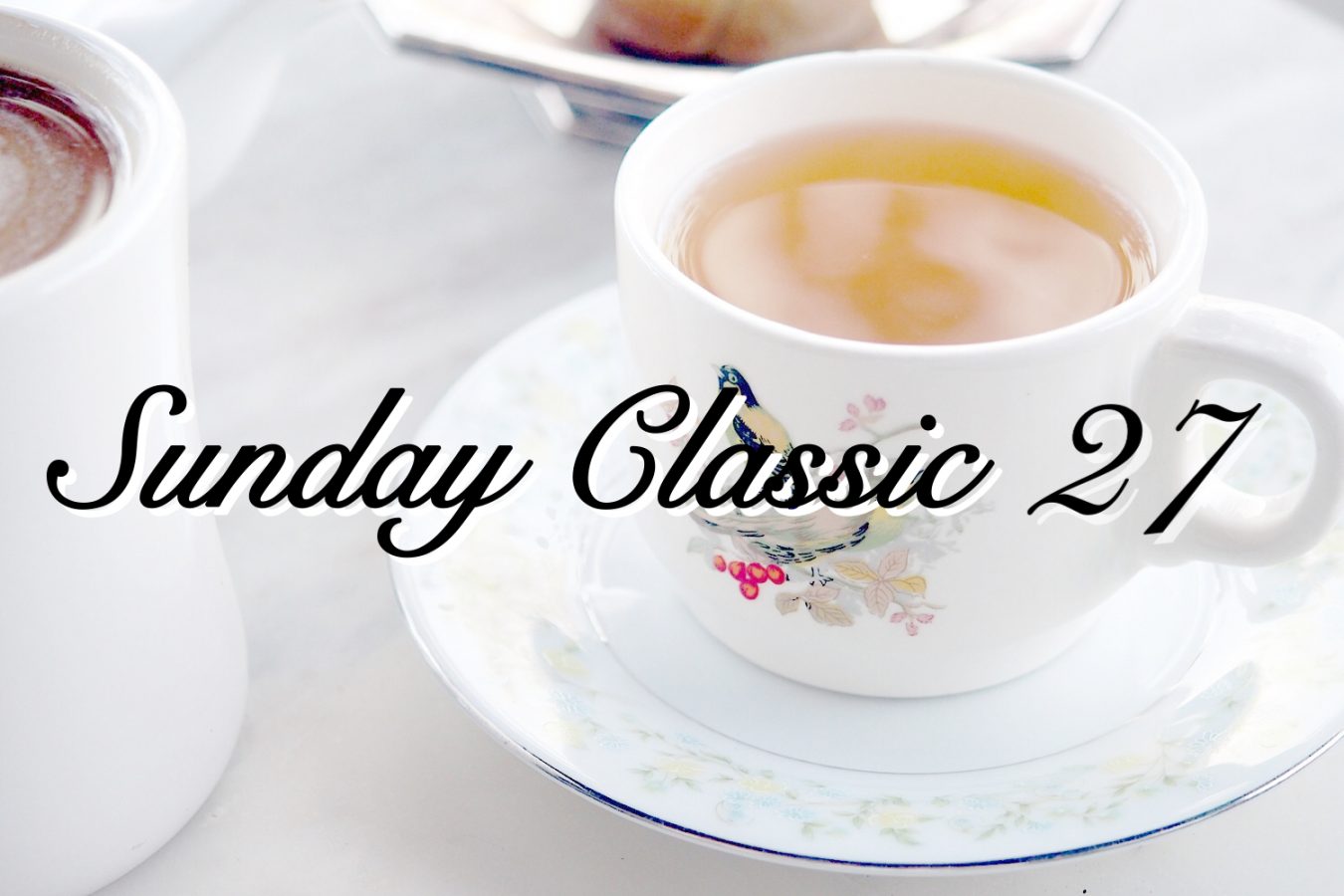みなさまごきげんよう。
前回、イタリアバロック音楽の絢爛(けんらん)な音楽を聴いていただきましたが、今日はフランスバロックのお勉強をしたいと思います。
本当ならスッとドイツの話にすり替えてしまいたいところなのですが、なんせフランスのバロック音楽にはジャン=バティスト・リュリ(1632〜87年)、フランソワ・クープラン(1668〜1733年)、そしてジャン=フィリップ・ラモー(1683〜1733)という偉人たちが名を連ねているものですから…。
フランスのバロック音楽は、本国では「ヴェルサイユ楽派の音楽」と称されているようです。この時代のフランス音楽はルイ13世〜15世の宮廷を中心に展開され、17世紀頃にイタリアからやってきた「オペラ」をフランス独自のものに確立したのがリュリなんだそうです。
ヴェルサイユ楽派の音楽
さてここで紹介するのは、現在でもよく演奏されるクープランから「クラヴサン曲集」。このクラヴサン曲集は全4巻からなり、230曲以上の小品が組曲(オルドルと呼ばれる)を構成しています。
「クラヴサン曲集」より第2巻 第6組曲 第5曲 /フランソワ・クープラン
ちなみにクラウザンとはチェンバロを意味するフランス語。ピアノで聴くのとはだいぶ雰囲気が違うでしょうからいつか生チェンバロで聴いてみたいものです…。
「クラヴサン曲集」より第3巻 第13組曲 第4番/フランソワ・クープラン
バロックらしい繊細な装飾音が素人から見ても魅惑的だなあと思います。
クープランはオペラには手を出さず、教会音楽、器楽合奏曲、そしてクラウザン音楽などを残しました。中でも器楽合奏曲は、ヴェルサイユの宮廷で貴族たちの食事の間にBGMとして演奏していたと言いますから、日曜の午後のティータイムにはまさにうってつけではないでしょうか?
『王宮のコンセール(Concerts Royaux)』/クープラン
優雅すぎる…(笑)
というわけで今日はフランスバロックのご紹介でした。次回はバッハに至るドイツ音楽を学んでいきましょう♪
ではお紅茶が冷めないうちにお楽しみくださいね。
ノリコ・ニョキニョキ
最新記事 by ノリコ・ニョキニョキ (全て見る)
- お子さんの初めてのピアノ教室はどう選ぶ? 音楽家へのアンケートをもとに考えてみた - 22.03.03
- 「ピアノを学びたいすべての人に、チャンスを」ベルリン発・ピアノ練習アプリflowkeyの生みの親ヨナス氏の願いとは(PR) - 20.12.22
- 「動画配信をわたしもやるべき?」に答えます。悩める音楽家への処方箋 - 20.05.20
- 音大生でよかった、と思える就活を。音大生就活を支援する『ミュジキャリ』立ち上げの想いとは - 20.05.01
- 完全無欠な演奏技術に奥深い音楽知識。ピアニスト阪田知樹が進化し続ける舞台裏に見えた4つの愛とは - 20.03.28