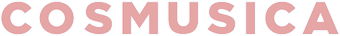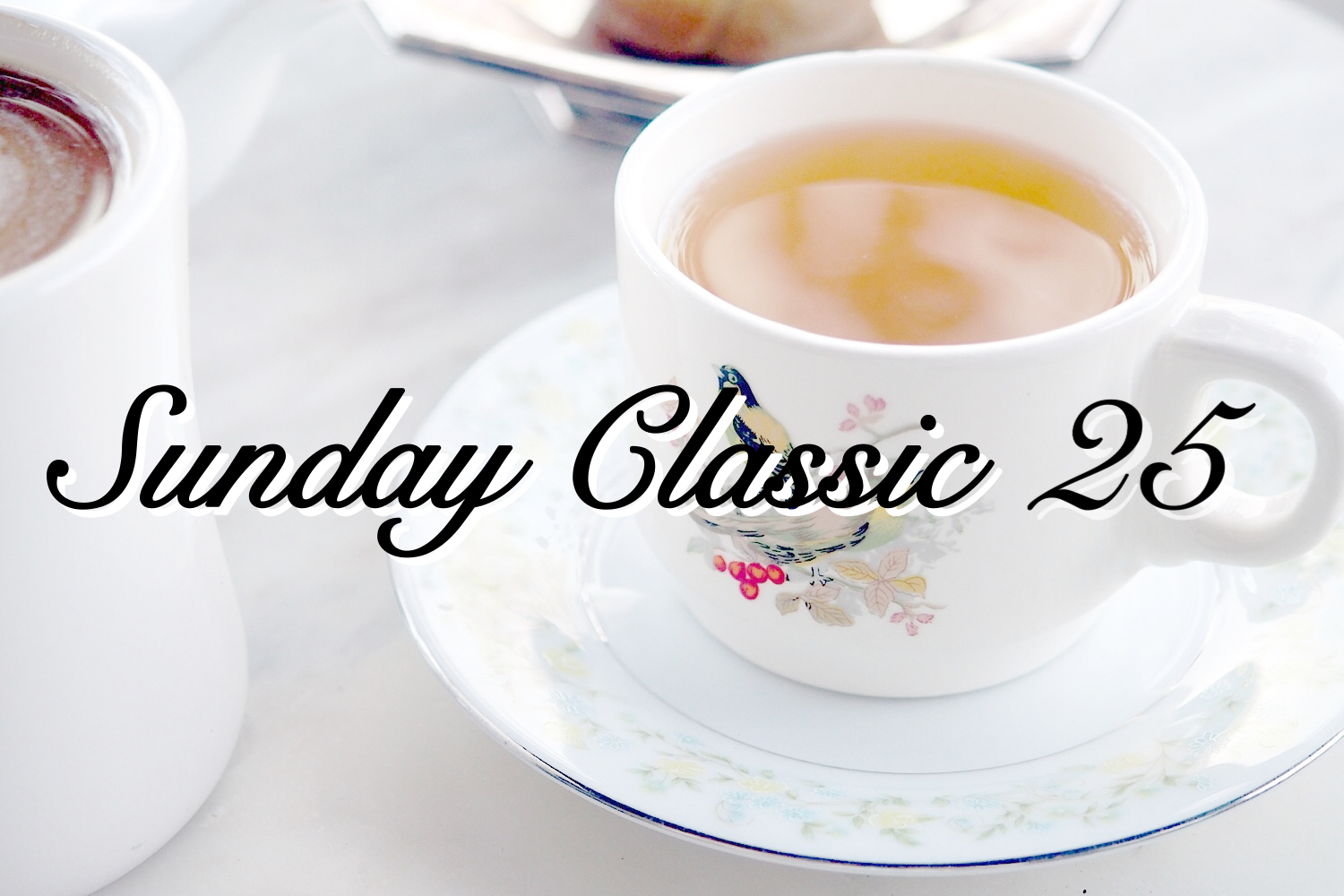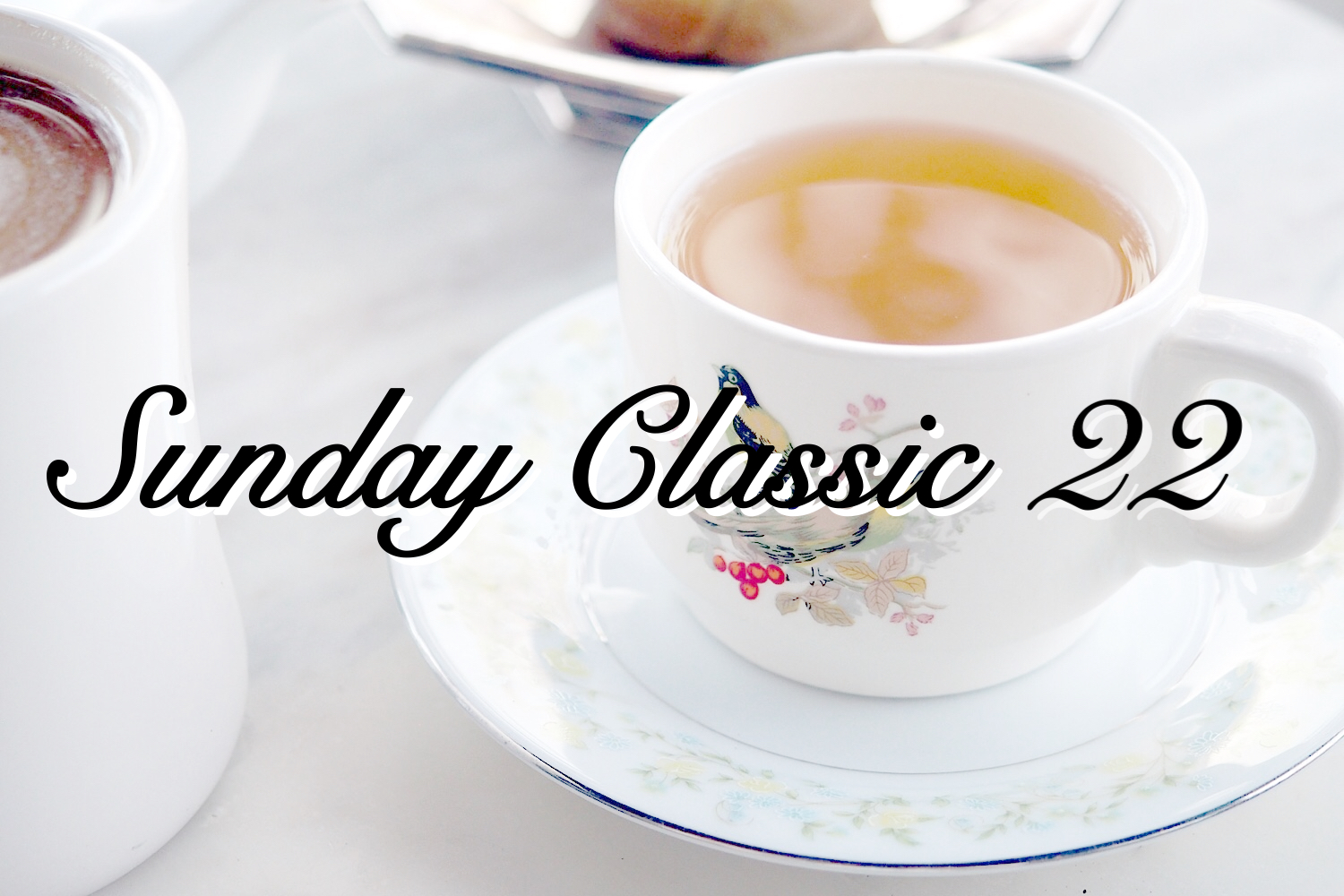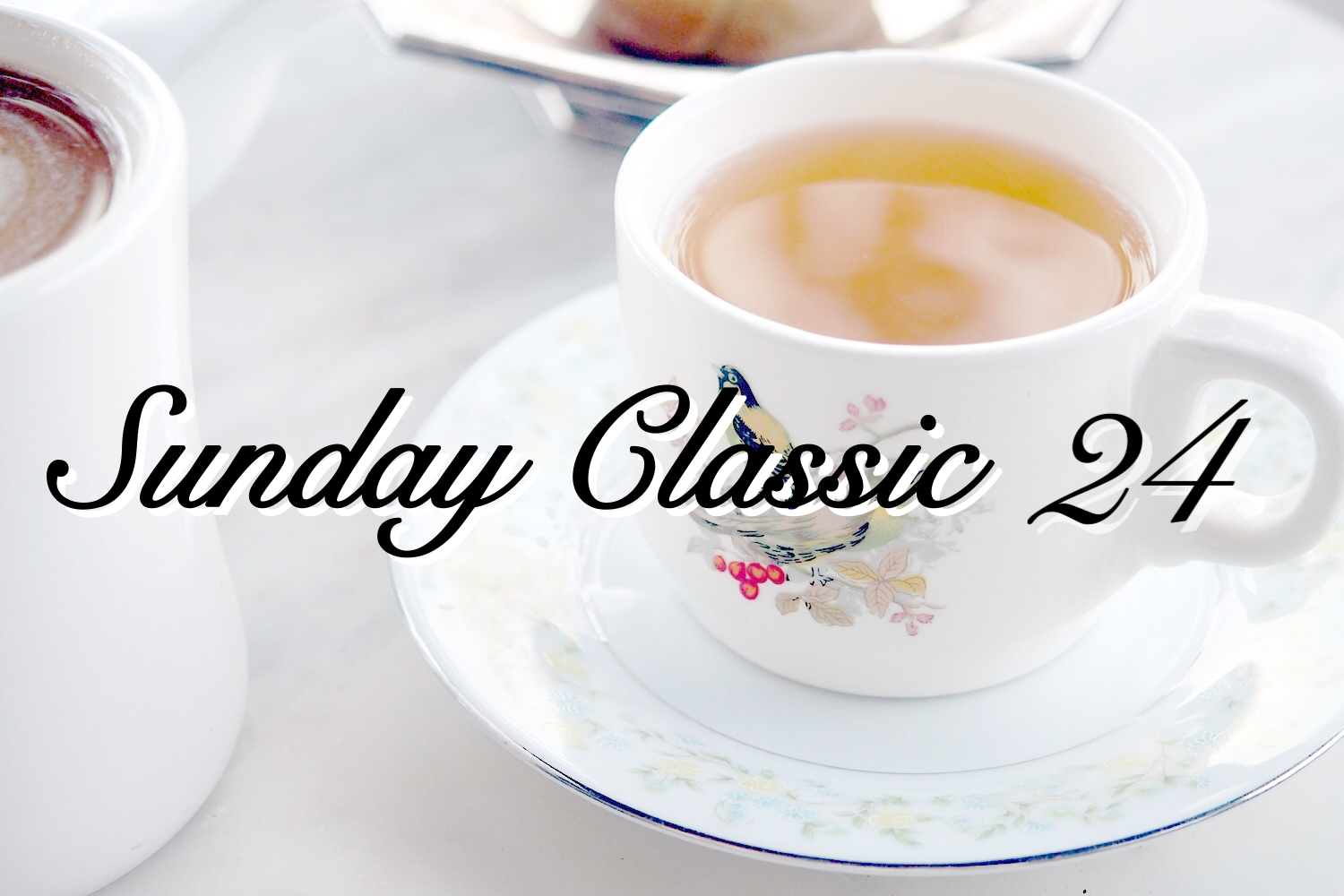キター!!!! 今週で第8回となるSunday Classic、今日からいよいよ古典派へと話を進めて参ります。
書籍『一年でクラシック通になる』(著:山本一太)によると、
バロック音楽が「通奏低音を軸にしたポリフォニックな調性音楽」だとすれば、古典派(そしてそれに続くロマン派)の音楽は、「ソナタ形式を中心とするホモフィニックな調性音楽といえるでしょう。
とあります。ポリフォニーは複数の声部が同時に進行しますが、ホモフォニーは端的に言ってしまえば旋律+和声(伴奏)の形をとっています。誤解を恐れず言えば、聞き慣れた音楽といってしまっても良いかもしれません。
また、ソナタ形式というのは、多楽章形式の楽曲の第一楽章で用いられる形式のことで、対比的な第一主題と第二主題が現れる「提示部」、それに続く「展開部」、そして最後に提示部を少し簡略化した「再現部」が現れるというものです。ちなみに芸大作曲科の入試では8時間かけてソナタ(他の形式のこともある)を書きますよ。
ということで、今日から3回かけて、ウィーン古典派を代表する作曲家、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの3人を取り上げていきます。
交響曲の父 ハイドン
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732〜1809)は、数多くの交響曲、弦楽四重奏曲を作曲して、交響曲の父、弦楽四重奏曲の父と呼ばれています。
ハイドンの偉業について語るとおそらく簡易的に書いても5000字はくだらないので例のごとくいきなり楽曲紹介をします。
交響曲第104番(1795年)
この曲はハイドンが書いた最後の交響曲。12曲に及ぶロンドン交響曲の最後を飾ることから『ロンドン』の愛称で知られています。
さきほどのソナタ形式を頭に思い浮かべながら第一楽章を聴いてみてください。ニ短調の序奏の後にニ長調で始まるのが、第一主題です。転調のあとは木管楽器で再び第一主題を提示。第二主題は木管+弦楽で提示されています。
その後は展開部へ。第一主題の後半のリズムを使って、ロ短調で始まります。展開部はオーケストラの全奏。そして再現部は第一主題が再び現れます。こうしたルールを知った上で楽曲を鑑賞すると、知らないで鑑賞するのとはまた別の楽しみ方ができますよね💡
それでは今日はこのあたりで。次週はモーツァルトの話題でお会いしましょう!
ノリコ・ニョキニョキ
最新記事 by ノリコ・ニョキニョキ (全て見る)
- お子さんの初めてのピアノ教室はどう選ぶ? 音楽家へのアンケートをもとに考えてみた - 22.03.03
- 「ピアノを学びたいすべての人に、チャンスを」ベルリン発・ピアノ練習アプリflowkeyの生みの親ヨナス氏の願いとは(PR) - 20.12.22
- 「動画配信をわたしもやるべき?」に答えます。悩める音楽家への処方箋 - 20.05.20
- 音大生でよかった、と思える就活を。音大生就活を支援する『ミュジキャリ』立ち上げの想いとは - 20.05.01
- 完全無欠な演奏技術に奥深い音楽知識。ピアニスト阪田知樹が進化し続ける舞台裏に見えた4つの愛とは - 20.03.28