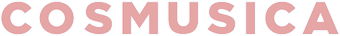こんにちは。ヴァイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆です。
この連載をはじめてまもなく1年が経ちます。そして全6曲のうち、前回までで半分の3曲を終えることができました。この連載は学習者にとってメジャーな順番に曲を取り上げることにしていますが、実を申せば、先の3曲はどちらかというとわたしが好まない3曲です(苦笑)。
むしろそれでよくこれまでバッハへの情熱を失わなかったな、と我ながら思いますが、嫌いなわけでもない上に、全曲制覇したいという思い、全曲を学んだときにこそ見える景色があるはずだと思ったので、せっせと譜読みをしてきたのでした。
今日からはわたしが一番好きな、ソナタ第2番を見ていきましょう。
ソナタ第1番との類似点
View this post on Instagram
無伴奏ソナタ第2番は、同じく無伴奏ソナタの第1番(▷卑弥呼のバッハ探究6「無伴奏ソナタ第1番 アダージョ」)とよく似ています。レチタティーヴォ的に語る緩やかな第1楽章、軽快なフーガの2楽章に、まろやかな長調の3楽章と、急速な4楽章という構成です。また1番は調性がト短調、2番はイ短調で、どちらもヴァイオリンにとってとても鳴らしやすい、なんとも親切な調であります。
1番の1楽章『アダージョ』に比べ、より落ち着いた性格を持つ2番の1楽章『グラーヴェ』。でもどちらも同じ4分の4拍子です。比較したときにどのような印象をもつでしょうか?
そもそも“Adagio”というイタリア語は「くつろぐ」という意味を持っているのに対し、“Grave”は「荘重に」という意味があります。どちらかというと2番の1楽章のほうが、より真面目ちゃん(しかもちょっと頑固)なように思います。
「木を見て森を見ず」にならないために
View this post on Instagram
おさらいで心掛ける点は基本的にアダージョに同じですが、強いて言うとグラーヴェのほうが音数が多い上にテンポも遅いので、より拍子感に気を遣う必要があるでしょう。
ゆっくりしていて細かい音が多い曲は、「木を見て森を見ず」な状態になりがちです。そんなときはまず、譜面台から物理的に離れて立って、遠くから楽譜を眺めてみてください。音楽を俯瞰できていないときは、この物理的な距離をとってみることが、シンプルながら有効な方法です。
曲の大きなまとまりは? 和声の流れは? 自分がついつい迷子になってしまう箇所は? ときには楽器を肩からおろして自問してみると、ふとアイデアが湧くこともあります。
この接続は…!
このソナタ2番に固有のチャームポイントは、グラーヴェの終わり方でしょうか。ドミナントの和音(お辞儀の和音です)で終わるグラーヴェは、次のフーガが開始すると和声が解決を迎える仕組みになっています。だからこの2曲は、ほぼ休みなしに続けて弾くことが求められます。

グラーヴェの最後のプラルトリラーは、上にも下にもダブルでついています。運指に完全5度が含まれるせいでちょっとミッションインポッシブルなトリルですけれども、わたしはがんばってダブルトリルを入れるのが好きです。でも、上のトリルだけ入れる方のほうが圧倒的に多いです。
View this post on Instagram
さぁフーガにつなげよう
というわけで、グラーヴェはフーガにそのまま音楽を引き継ぎます。
短調ではあるのですが、わたしはこの曲に “暗さ” よりは “冷静な前向きさ” のような感覚を抱いています。浮かれ調子ではなく、けれども極端な悲観もせず。おそらくわたしがそう生き方をしたいと思っているせいで、わたしはこの曲に何かシンパシーを抱いているのだろうなぁと思います。
それでは次回は2つ目のフーガとともにお会いいたしましょう!
最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)
- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20
- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18
- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30
- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07
- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28