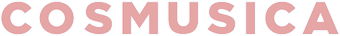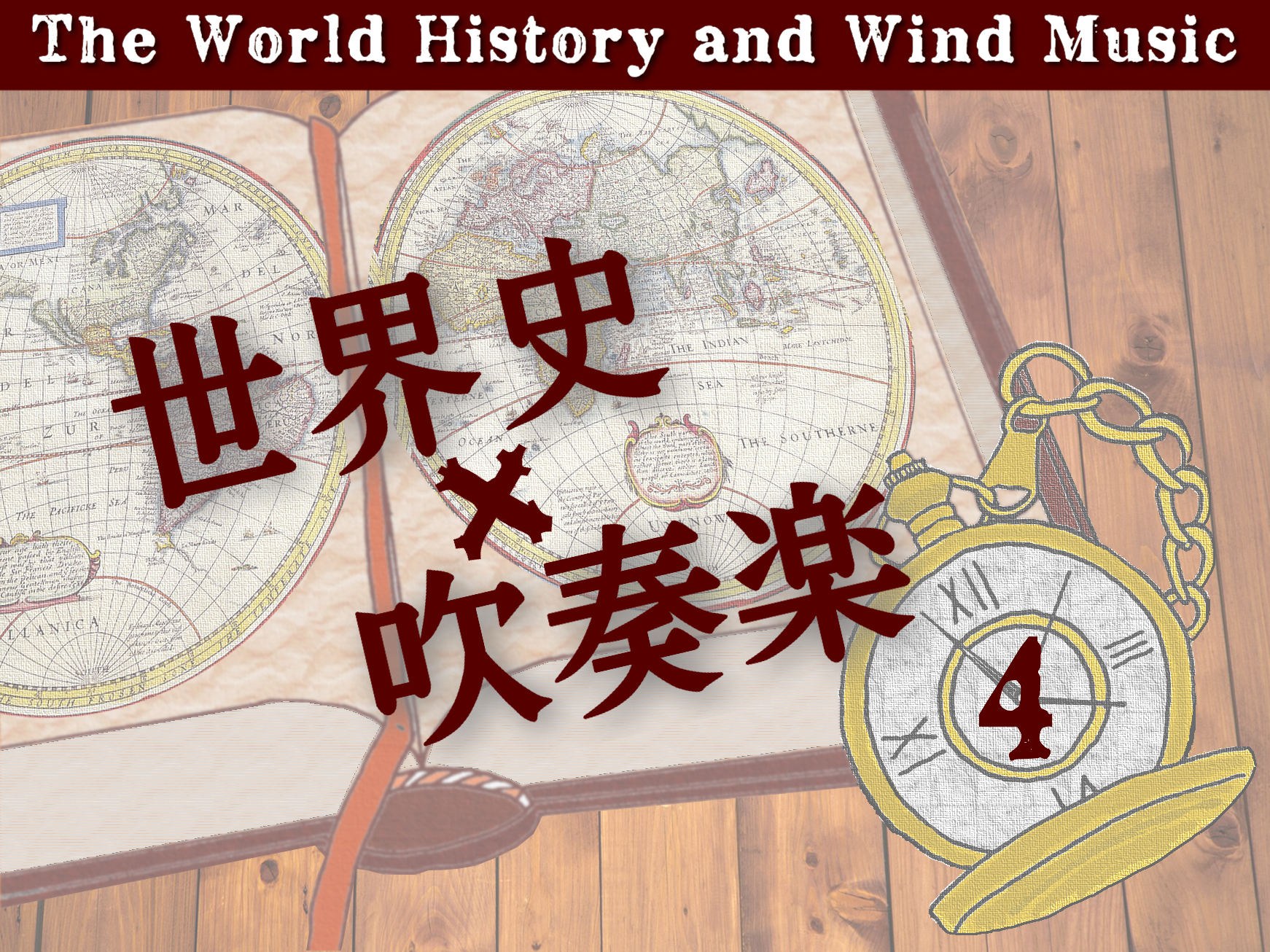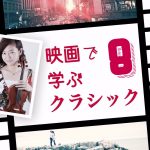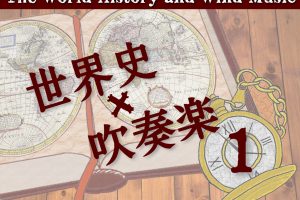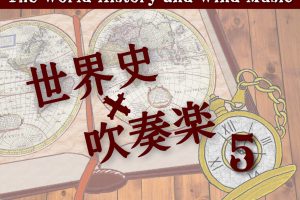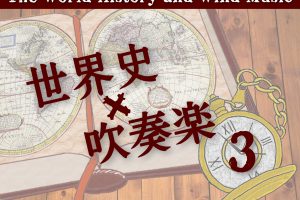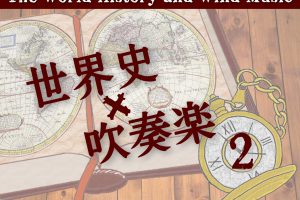ききどころ
交響詩「スパルタクス」は、この反乱劇を音楽で描いたものです。楽曲は3部構成となっており、それぞれ
- 剣闘士たちの世界
- スパルタクスと恋人の恋愛
- ローマ軍と反乱軍の戦い
が描かれています。
第1部〜剣闘士たちの世界
冒頭から力強くも重苦しく強奏されるC(ド)の音は、巨大な闘技場の扉が開き、生死をかけた戦いを前にした剣闘士の姿を思わせます。剣闘士の前に立場だかるものは恐ろしい猛獣なのか、それとも同じ奴隷として養成所に入れられた仲間なのか。
ティンパニの刻むリズムが冷たく緊迫した雰囲気を作り出す中、今か今かと戦いを待つ観衆の期待に応えるように奏でられる上行する音形は、戦いの幕開を知らせのように感じます。木管楽器のトリルに乗って顔を出す輝かしい金管楽器の響きは歓声でしょうか。第1部は観衆の見世物として死闘を繰り広げる剣闘士の姿が思い浮かびました。
そして決着がついたのか、再び力強い強奏で第1部は締めくくられます。

第2部〜剣闘士の恋を思わせるドラマチックな世界
フルートが奏でる自由なカデンツで開始される第2部は、多くのプログラムノートや解説に「スパルタクスと恋人の恋愛」を思い描かせるシーンだと書かれています。「愛のテーマ」とも呼ばれるこのテーマが、コールアングレに引き継がれ、形を変え第2部全体にわたり顔を出します。
第1部の世界観とは変わって優美でドラマチックな音楽は、まさにこの交響詩の聴きどころと言えるでしょう。そして、吹奏楽の中で唯一の弦楽器であるコントラバスがpizzicatoで奏でる「レーソーソード」という音形が木管楽器のアンサンブルを弦の響きで包み込みます。

第3部〜スパルタクスの反乱と誇り高き音楽
激しさと、生身の人間がぶつかり合う生々しさの中に、スパルタクスが反乱を起こした目的を感じさせる誇らしさや輝かしさも見える第3部。スパルタクスを指導者とする反乱軍の目的は、ローマ軍を打ち破り権力を握ることではなく、失われた自由を求めた反乱であり、奴隷たちを故郷に帰還させることが目的でした。
結果的に、スパルタクスは戦死し、最後は反乱軍も敗北してしまいますが、この戦いは奴隷たちが失われた自由を求め起こした、歴史上唯一の正しい戦争と評価され、スパルタクスの名は英雄として後世に語り継がれることになります。
最後は、これまで出来事を回想するように音楽が再現され、一気にエンディングへと駆け抜け、音楽で描かれたスパルタクスの反乱劇は幕を閉じます。
おしまい。
1988年に作曲された交響詩「スパルタクス」は、当時まだ若手作曲家だったヤン・ヴァン・デル・ローストの名を世界に知らしめるきっかけの作品となりました。
この作品のスコアには、イタリア語で
「オットリーノ・レスピーギへのオマージュ」 “un omaggio a Ottorino Respighi”
と書かれています。
レスピーギといえば、交響詩「ローマの松」がありますが、その第4部には「アッピア街道の松」という名がついています。アッピア街道といえば、古代ローマの進軍道路であり、反乱軍が磔にされいくつもの十字架が並んだ場所。そして、彼が自ら指揮をしたフィラデルフィア管弦楽団の演奏会プログラムノートを見てみると、
『ローマの松』では、私は、記憶と幻想を呼び起こすために出発点として自然を用いた。極めて特徴をおびてローマの風景を支配している何世紀にもわたる樹木は、ローマの生活での主要な事件の証人となっている。
とあります。ということはこの “松” は、ローマ軍がはるか果てまで進軍していく姿も、反乱軍を磔にした十字架がどこまでも並んでいる様子も、すべてこのアッピア街道で見ていたのでしょうか。
何か、繋がりがあるのかもしれませんね。きっと、正解はないと思いますが、こうなんじゃないかな? と自分なりに考えてみるのも、音楽を聴く楽しみのひとつです。
吹奏楽×世界史でお届けするこのコラム、次はどの時代へと向かうのでしょうか? 次回もどうぞお楽しみに。
最新記事 by 井口信之輔 (全て見る)
- 夏休み特集③ 吹奏楽部員に聞いた「吹奏楽コンクールの自由曲とその思い出」 - 18.09.02
- 夏休み特集② 後世に伝えたい、吹奏楽の古典的作品と隠れた名曲 - 18.08.27
- 夏休み特集① 吹奏楽コンクールで演奏されてきた、今もなお色あせない名曲 - 18.08.17
- 「吹奏楽指導に関わる仕事がしたい」と思っていた音大時代から今日まで取り組んでおいてよかった9つのこと - 18.04.13
- 忘れてはならない記憶と平和への思いを音楽に乗せて/福島弘和『ラッキードラゴン第五福竜丸の記憶』 - 18.02.10