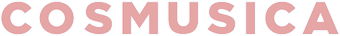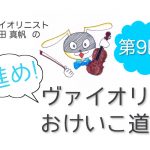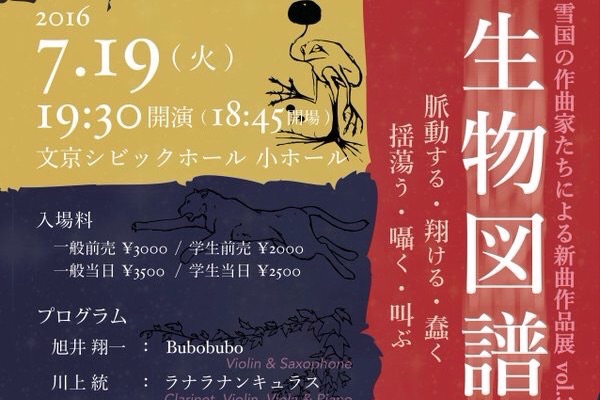こんにちは。邦楽演奏家の藤田和也です。
8月半ばに差し掛かり夏本番となりましたが、皆さんはお祭りなど行かれましたか? 焼きそばや綿あめといった露店、お神輿や笛、太鼓の音など、お祭りのイメージや思い出は人それぞれだと思います。
実はお祭りは、邦楽にも深く関係する伝統行事なんです。今回は、皆さんの知らないお祭りの本来の意味や音楽について解説していきます。
お祭り=お祀り?

元々、お祭りには「お祀り」という漢字があてられていました。「祀る」という漢字からも分かる通り、もともと、オマツリは神事の一部です。神社の神様に感謝したり、お祈りを捧げるのが本来のオマツリです。最近では神社などの関係ないお祭りもありますが、その場合はフェスティバルの意味が強いです。
また、お祭りには2~3年周期で行われる正式な「本祭り」と、「本祭り」のない年におこなわれる簡略な「陰祭り」があります。
お神輿のヒミツ

日本全国いろいろなお祭りがありますが、お神輿を担ぐお祭りを見たことがある方は多いはずです。お神輿を英語でいうとPortable Shrine(ぽーたぶるしゅらいん)。直訳すると、携帯神社です。
そう、お神輿とは神社なのです。お神輿は、普段神社に祀ってある神様を乗せて、発展した町内を見ていただくなどの意味があります。こうした神社のお神輿のことを「本神輿」とも呼び、2~3年周期で担ぎ出されます。また、先ほどご紹介した「本祭り」は本神輿が出る場合が多いです。
ちなみに余談ですが、獅子舞に頭を噛んでもらうと1年間無病息災というのを聞いたことはありませんか? これも、獅子舞の頭の中に神社のお札が入っているから、そのようなご利益があると言われているんです。
お祭りの音楽

お祭りに欠かせないもの、それは笛・太鼓の音ですね。お祭りに行くと、よくテンツクテンツクと奏でられているのを耳にすると思います。地域によってさまざまな呼ばれ方がありますが、お祭りの際に演奏される囃子(はやし)を祭囃子(まつりばやし)といいます。
囃子については、前回の記事で簡単に解説しているので、ぜひご覧ください。
東京のお祭りで演奏されるのは、江戸祭囃子と呼ばれる囃子がほとんどで、笛1人、締太鼓2人、大太鼓1人、当り鉦* 1人の編成で、お神輿を担いでいるときなどによく演奏されます。
*当り鉦:金属製の打楽器の一種。円形で郷土芸能の音楽や祭囃子の演奏に使われる。
神社などでは、神楽殿(かぐらでん)という能舞台のような場所で神楽(かぐら)が舞われていることがあります。神楽とは無言で演じられる仮面劇で、主に日本書紀や古事記を題材にした演目を演じています。祭囃子とは違う楽器で大拍子(だいびょうし)、笛、大太鼓の演奏の中、無言劇が進んでいきます。お神輿のときのお囃子と違い、神社の風情あふれる様な雰囲気の囃子です。
江戸三大祭り
東京では江戸時代に町が大きく発展し、お祭りもとても大きくなっていきました。中でも江戸三大祭りと呼ばれるお祭りを紹介したいと思います。
神田祭
場所 神田明神
時期 5月中旬
2年に一度、本祭りが執りおこなわれ、神輿や曳き物(ひきもの)などの豪華な大行列が、神田・日本橋エリアを練り歩きます。 神田明神は天平2年(730年)に現在の大手町に創建され、元和2年(1616年)に江戸城の裏鬼門守護地となる、現在の地に遷座されました。周辺の地域で約200基のお神輿が出る大きなお祭りです。
山王祭
場所 日枝神社
時期 6月初旬~中旬
山王祭の一番の見どころは何と言っても2年に一度行われる神幸祭です。神幸祭は大祭のときに行われ、神田祭と年ごとに交代なのですが神輿も山車も違うのでそれぞれ違った雰囲気の神幸祭が楽しめます。例祭の神事以外でも茶席や野点の席が設けられたり、神楽囃子や山王太鼓の演奏などが複数日にわたって催されています。
深川八幡祭り
場所 富岡八幡宮
時期 8月中旬
1624年に創建された由緒正しい富岡八幡宮で、お盆休みにあたる8月15日を中心に執りおこなわれるお祭りです。通常「水掛け祭り」ともいわれております。とにかく暑い時期のお祭りなのでたくさんの水を神輿にむかって沿道から掛けます。また、露店も多く出るのでお祭りの雰囲気を楽しみたい方にもおすすめです。
以上が江戸三大祭りと呼ばれるお祭りですが、他にも浅草の三社祭りや鳥越神社のお祭りなど有名なお祭りは沢山ありますので興味があればぜひチェックしてみてください!
日本には各地にさまざまな形態のお祭りがあります。旅行がてら見学するも良し、近所に足を運ぶも良し、自分なりのお祭りの楽しみ方を見つけてくださいね。
藤田 和也
最新記事 by 藤田 和也 (全て見る)
- 伝統行事をもっと楽しもう! 知っておきたいお祭りのあれこれ - 16.08.18
- 知っているようで知らない? 邦楽の全体像を学ぼう - 16.07.29