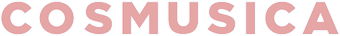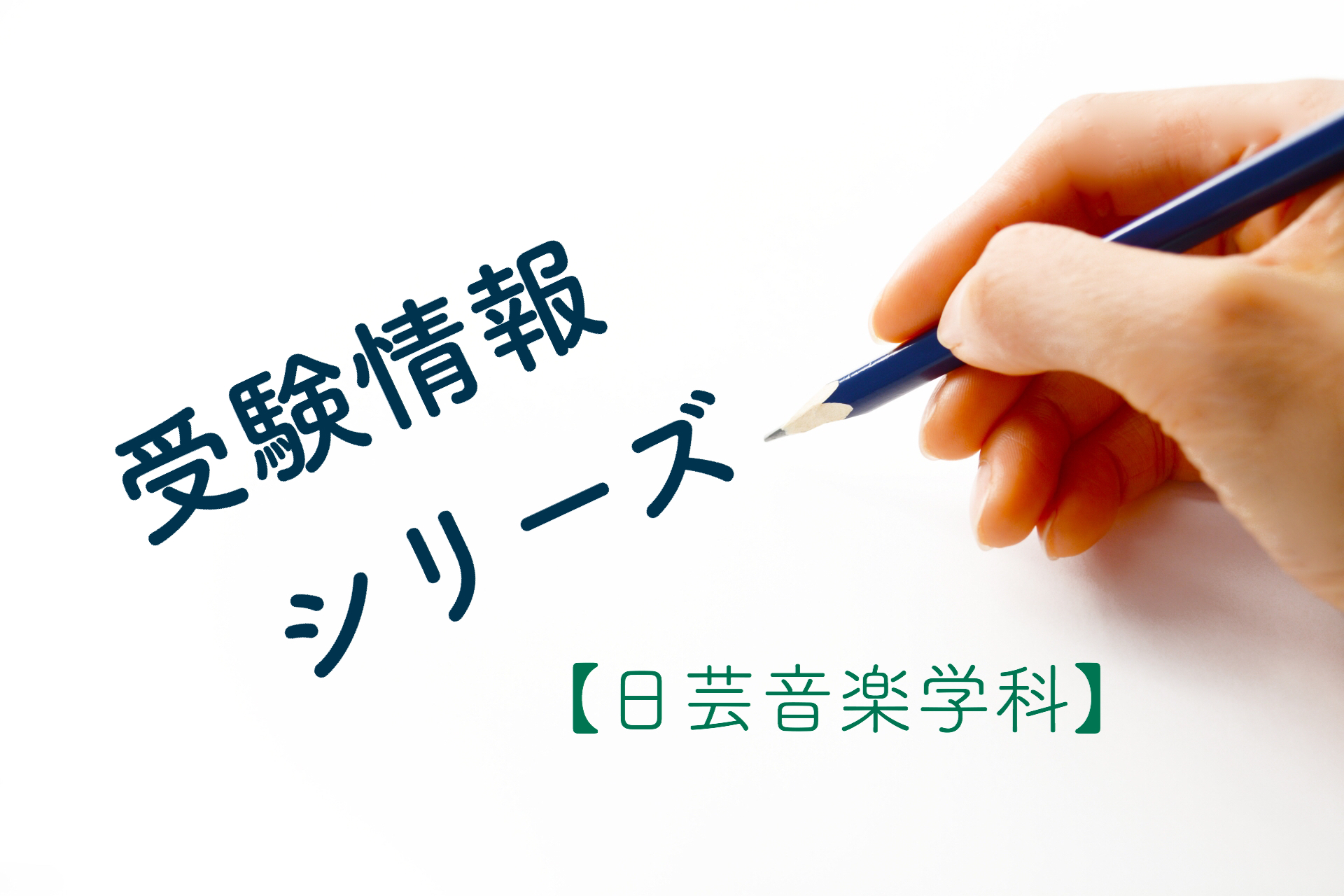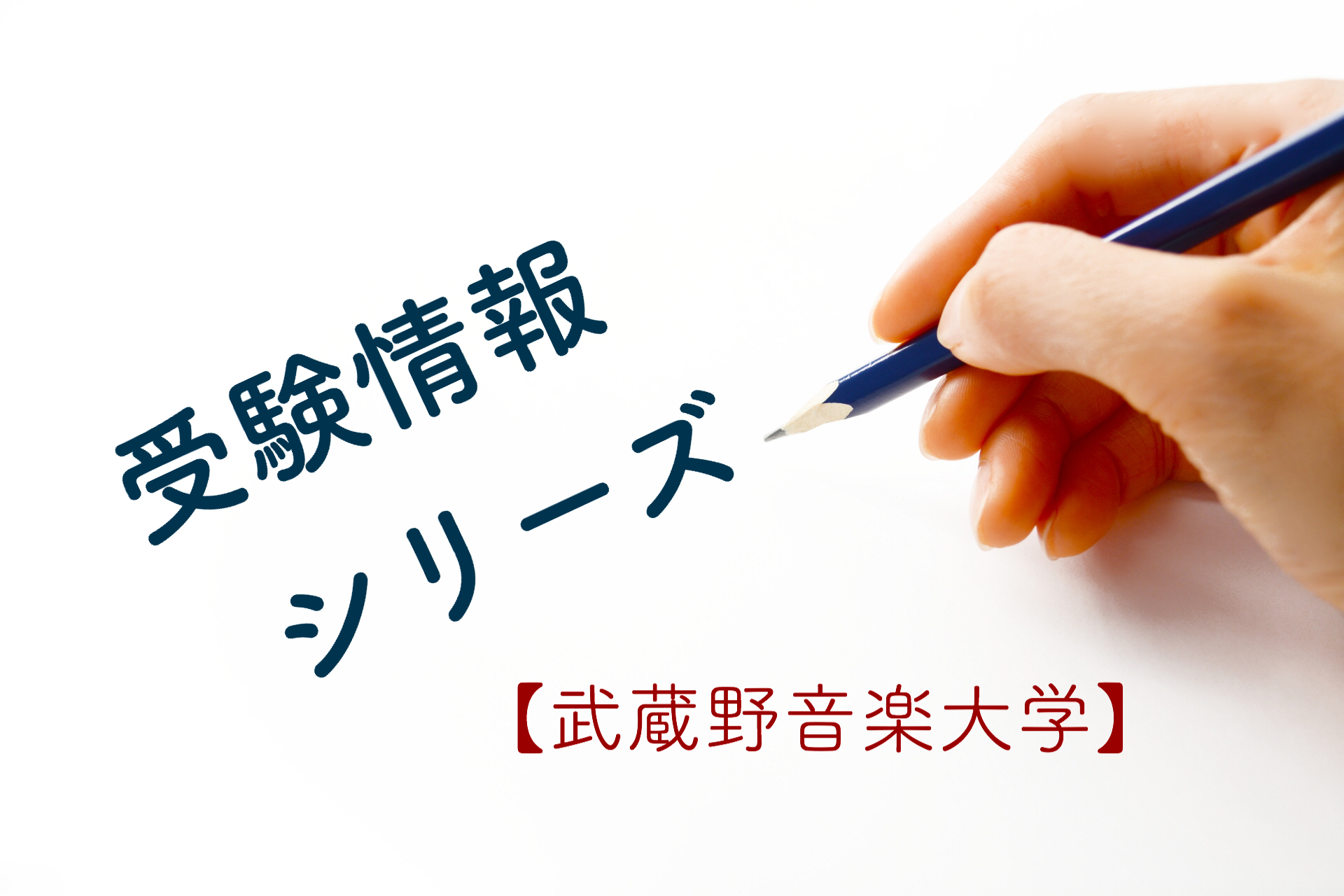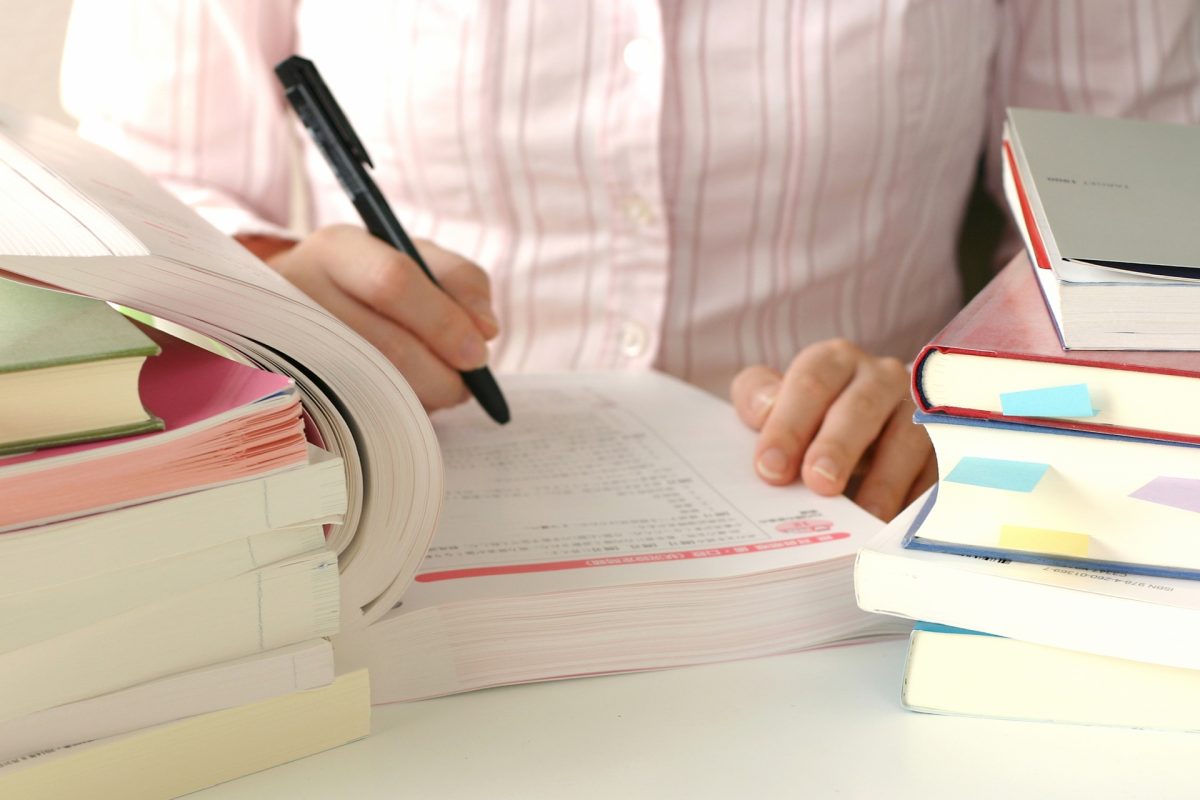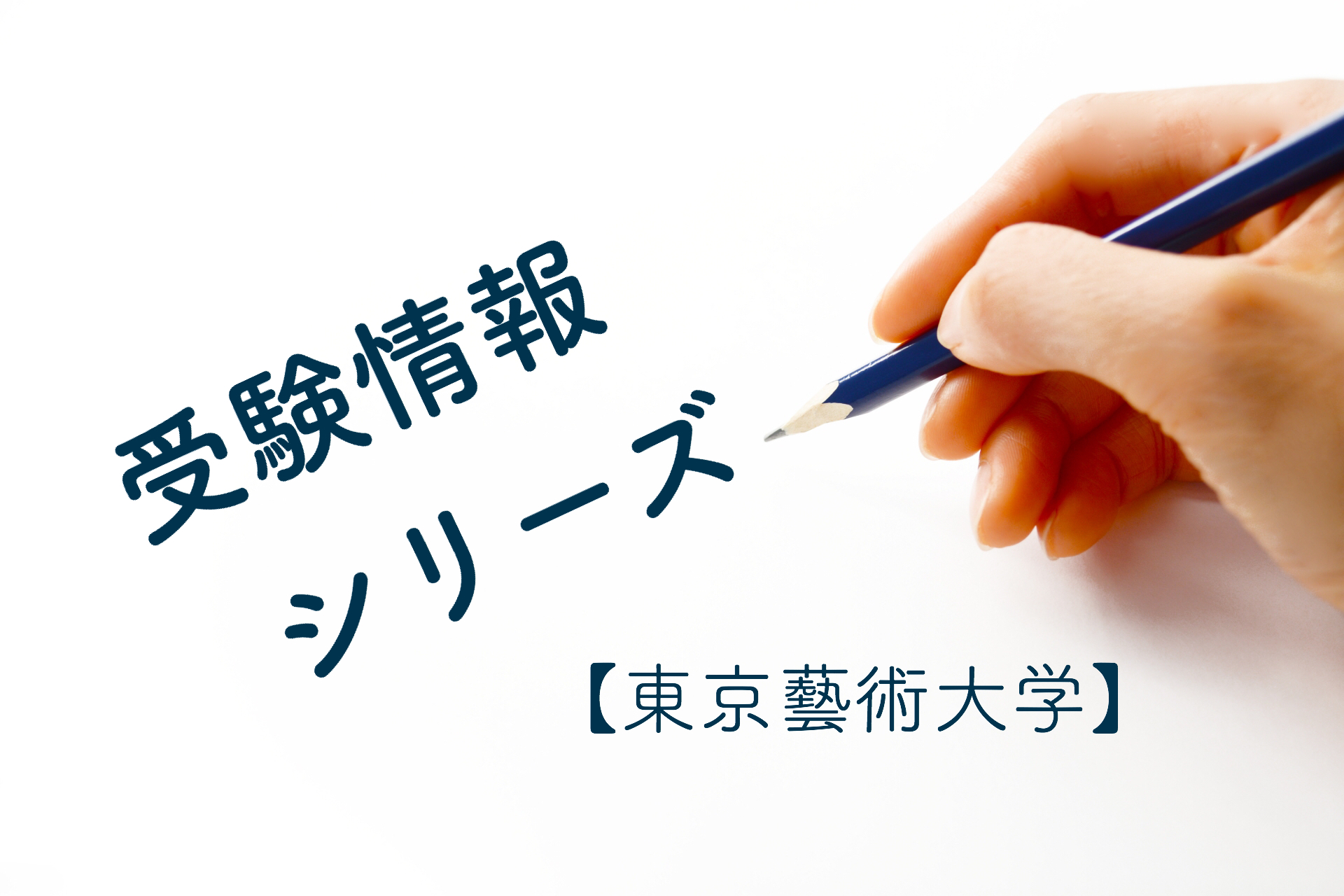「どうして勉強しなきゃいけないの?」は悩める学生のテッパンの問いですが、音楽界隈の学生にとっては「どうしてソルフェージュをやらなきゃいけないの?」という疑問も多いのではないでしょうか。
本日は「自称・得意科目はソルフェージュ」なワタクシが、ソルフェージュの中でも苦手意識を持つ人が多い「クレ読み」ができると、どのようなシーンで役立つのかお伝えしたいと思います。
譜読みが早くなる💡
クレ読みが早くなれば、譜読みが早くなります!
たとえば、こんなに目がチラチラする譜面も…

(使用楽曲:メンデルスゾーン 交響曲第 4 番『イタリア』より第 3 楽章、第 2 ヴァイオリン)
まず視覚で和音のまとまりをつかみ、聴覚で和声を感じれば、あら不思議、音をひとつひとつ見るよりずっと早く音楽をつかめる=弾けてしまうのです。
特にピアノ作品の中でも幼少期に触れる曲では、左手はアルペジオを担うことが多いので、ピアニストはほかの楽器の人よりも和声感が育つのが早い傾向にあると思います。
オーケストラや室内楽で低音や中声部を受け持つ楽器の人は、視覚で和声をつかめるようになると譜読みが格段に楽になるはずです! クレ読みで、 音程の反復練習が嫌いな人は少なくないと思いますが、この幅は 6 度だ! という見え方を手に入れるためですので、ぜひがんばってください!
アンサンブルで役立つ🌟

譜面を音程でとらえられるようになると、和声的に肝心な音が見分けられるようになるので、相手と合わせやすくなります。
ここだけの話……うっかり音を間違えてしまっても、同じ和声内ならごまかせるというか……
相手に寄り添う柔軟さを見せるには、音符の緩急を見抜いてこそ。クレ読みに強くなることで、譜読みが楽になる分、楽譜から情報を読み取ることに意識を注ぐことができます。
初見に強くなる💪
クレ読みができる人というのは、楽譜を見る視点を変えるのが上手です。というのは、まずはじめに譜面全体をとらえる「マクロ」の視点を使い、次にひとつひとつの音符を見る「ミクロ」の視点で音を読んでいきます。ピントを調整することで、譜面の段が変わるところでも止まらずに先を読んでいける、というカラクリです。
つまり、だれもが「マクロ」と「ミクロ」を使い分けているはずなのですが、焦っていたり、緊張しているとうまくピント調整ができなくなって、「初見苦手だぁ」という現象が発生します。
つまりクレ読みは、ピント調節の訓練とも言えるかもしれません。
もちろん初見に強くなるためには、読んだ音符を手や唇に落とし込む訓練も必要ですが、まずはクレ読みを鍛えることで、視覚を育ててみてください💫
かくいうわたしも、音楽高校に入って初めてクレ読みに取り組んだ頃はとても苦手で、楽譜を「マクロ」で捉えることが全くできませんでした。そこで以前からお世話になっているソルフェージュの先生のところに駆け込んだら、「目が悪いならメガネかけてやりなさい」と言われました。
そう、目が悪いとどうしても視界が狭くなりがち。ああ、もちろん、コンタクトでも大丈夫です!
最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)
- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20
- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18
- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30
- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07
- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28