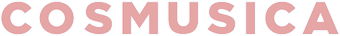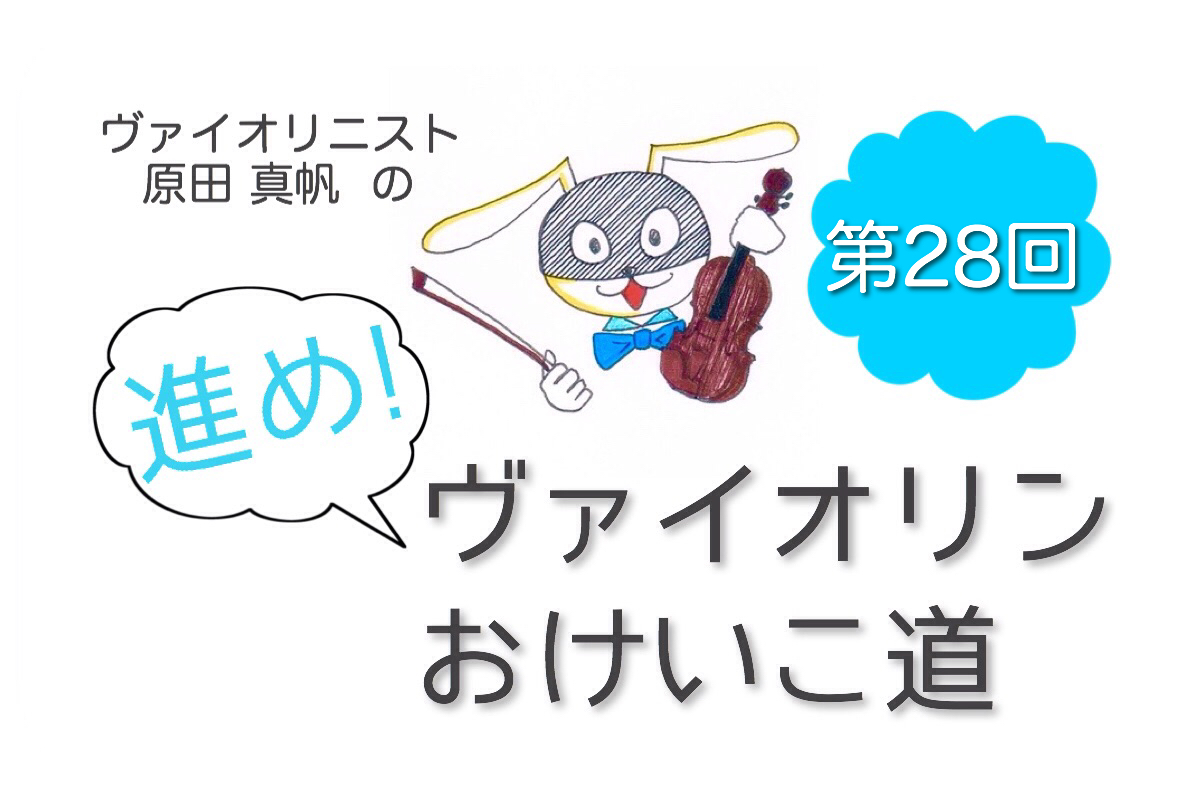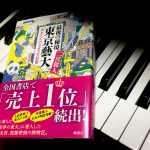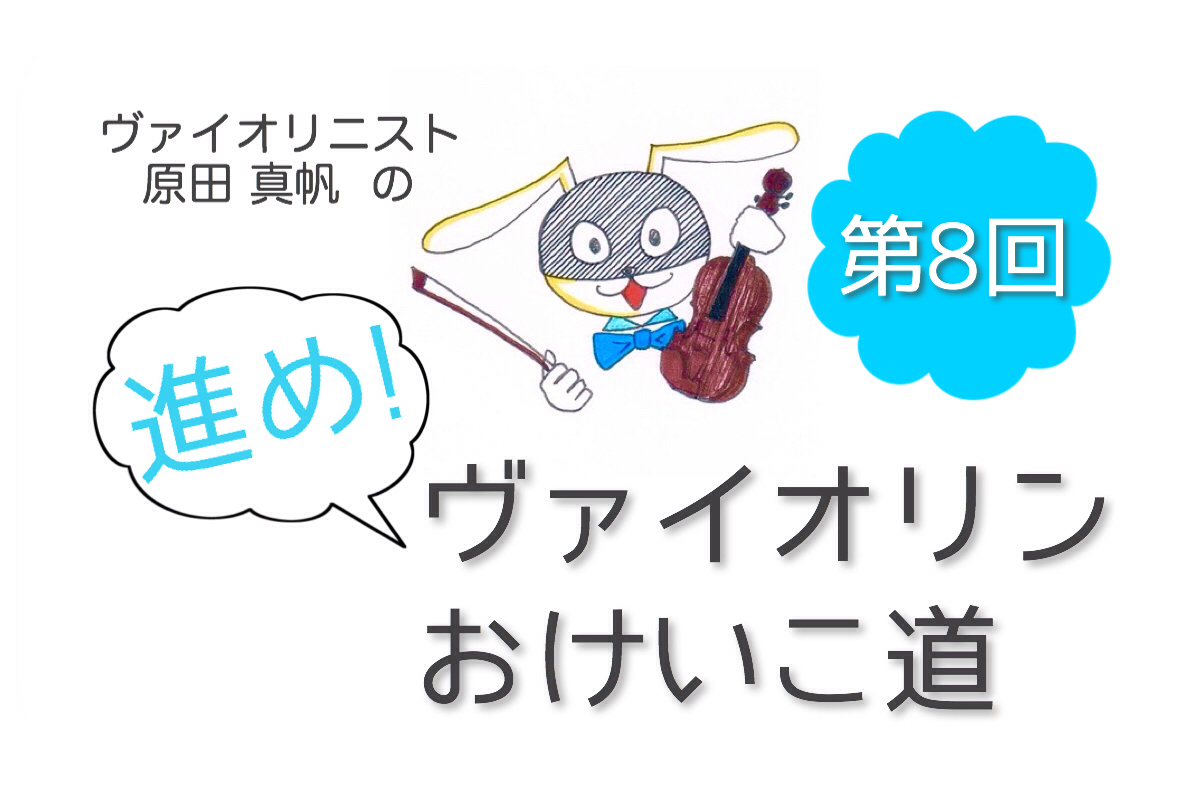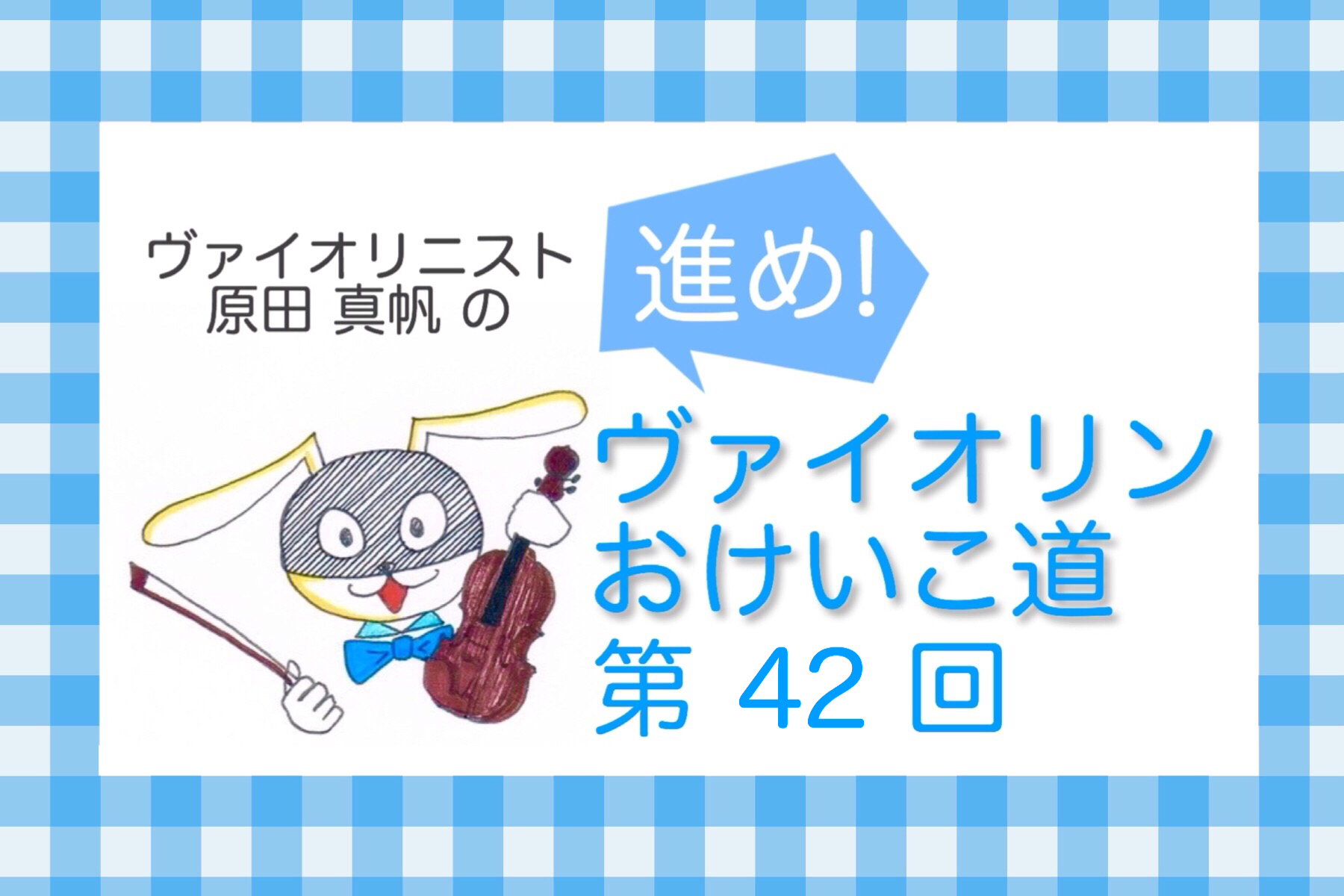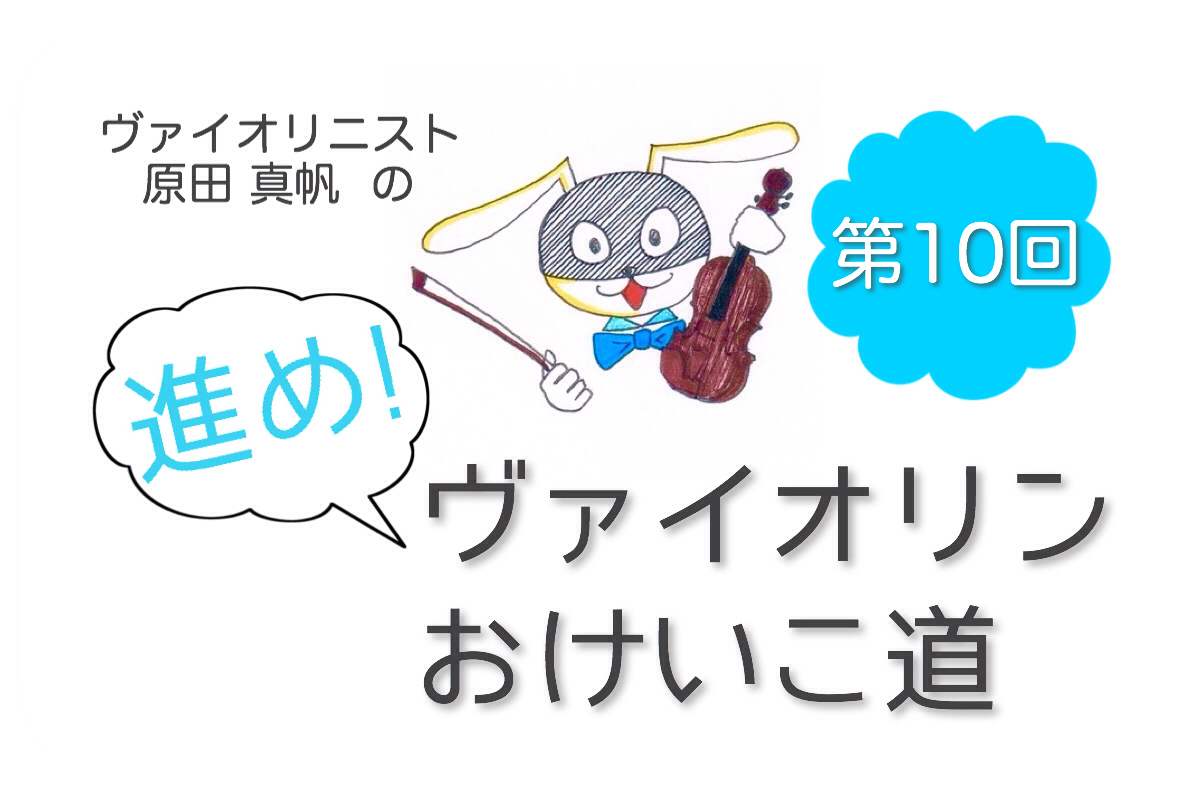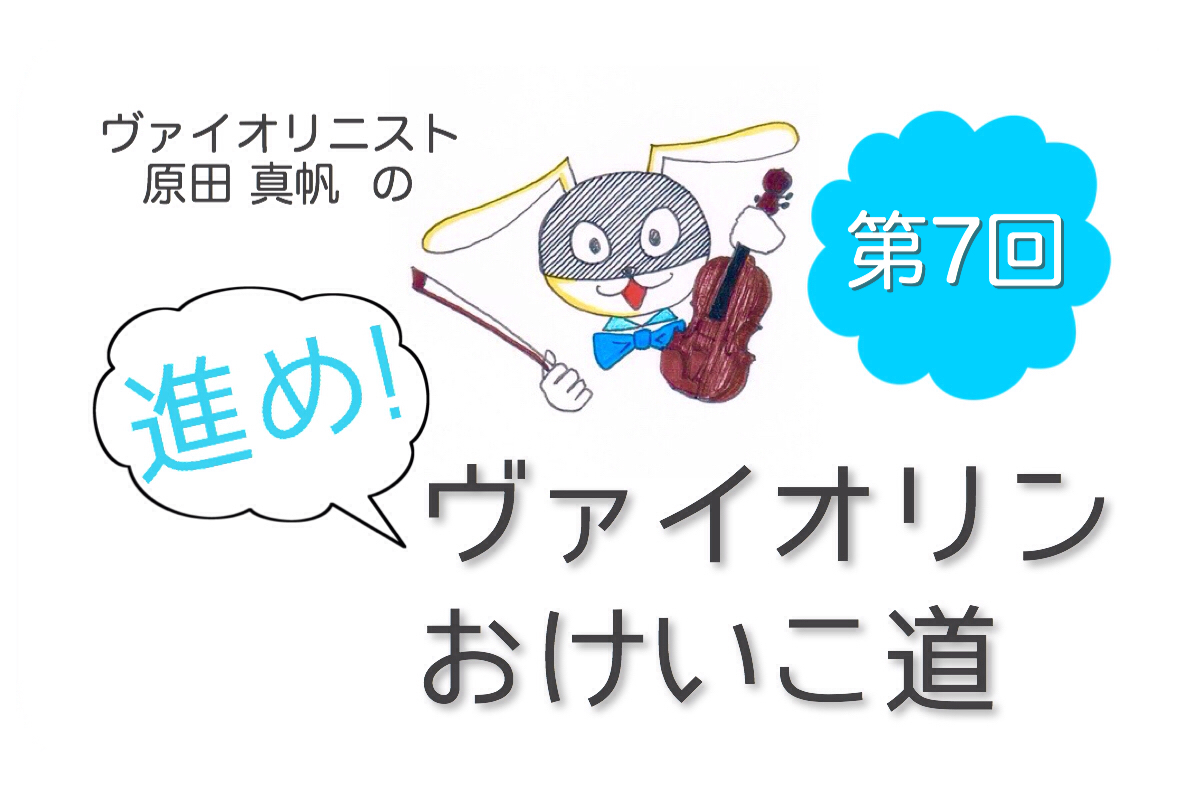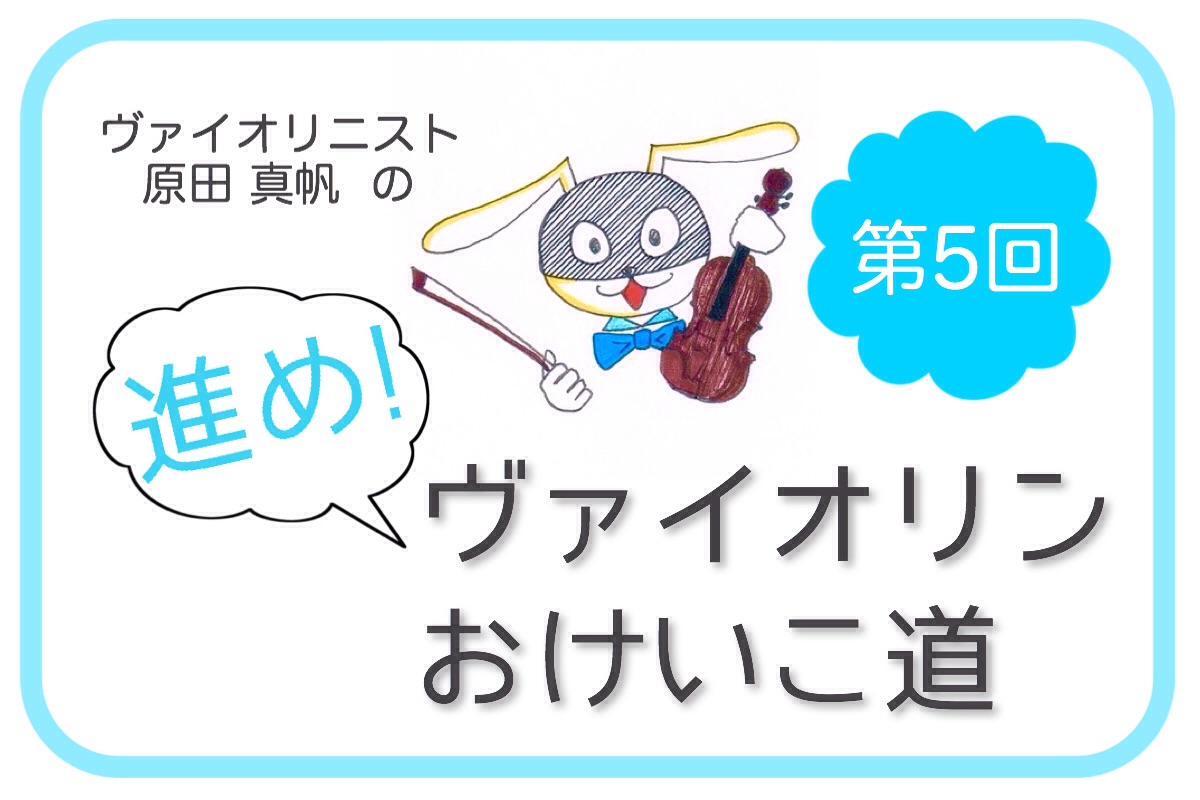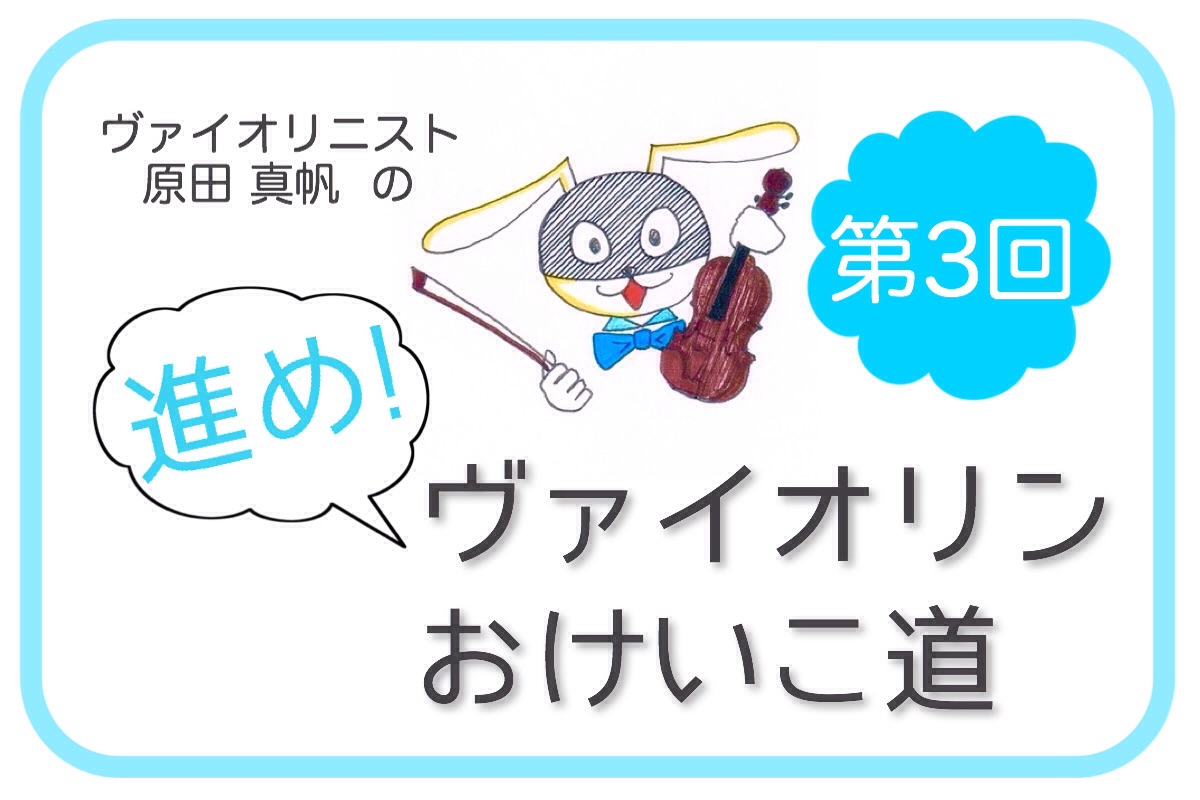新年あけましておめでとうございます。おけいこニストのみなさまは、年越しはいかがお過ごしでしたか? 今年もどうぞ「おけいこ道」をよろしくお願いいたします。
新年最初のテーマは発表会について。「親子共演」の視点から見ていきましょう。
お母さまはピアノ弾き

世間的には楽器を始めると言ったらピアノの方がスタンダードなわけで、ヴァイオリンを始める場合、親御さんが何か楽器を演奏されるなど「音楽への関心が高い家庭環境」であるケースは少なくありません。「発表会でお母さまが伴奏をされるというのも珍しいことではない」と言うと語弊がありますが、門下の中で大概 2・3 組はいらっしゃると思います。
ピアノを弾けるお母さまは、実際に演奏家の方のこともあれば、ピアノ教室を開いている方や学校の先生だったり。わたしの場合、母はうんと初期の練習曲の伴奏程度しか弾けませんので本番で共演したことはありませんが、練習のとき母に伴奏をつけてもらえるのはとても楽しかったのを記憶しています。そのため親子で発表会に出ているペアを見ると、ああステキだなぁと憧れます。
ご自分の練習もしつつお子さんの練習を気にかけるのはなかなか大変ですが、親子での共演経験は大人になっても心に残るものなので、もしピアノを弾ける方ならぜひ弾いてあげてほしいなぁと思います。
お母さまはアナウンサー?!

親子共演というと「伴奏」が真っ先に浮かびますが、一度違う形の「共演」に遭遇して驚いたことがあります。
日頃お世話になっているピアノの先生のお教室の発表会で、アンサンブル隊員としてお手伝いにうかがったときのこと。お弟子さんのお母さまの中に元アナウンサーの方がいらして、出演者の名前を読み上げる影アナウンス(舞台袖の見えないところから聞こえる放送のこと)を担当されていました。
その方のお嬢さんは当時小学生で、ピアノは伸び盛り。初めてのピアノ三重奏に緊張しつつもリハーサルではしっかり弾いていたので、わたしは本番を楽しみにしていました。しかし彼女は本番で緊張のあまり、2 小節弾いたのち突然止まって最初に戻って弾き直しました。
これが本人としてはかなり悔しかった様子で、終演後楽屋にやってきて「もう一度弾きたい…」と言っていましたが、隣でお母さまが
「娘のアナウンスをしたときにわたしのほうも緊張してしまって、それが声で伝わってしまったんじゃないかなって…」
と言ってらしたのが非常に印象的でした。
確かに読むほうもいくら仕事とはいえ、娘のこととなると平常心を保つのはなかなか難しいでしょうし、娘ならお母さんの声から心情の機微、感じちゃうかもしれませんね。いやむしろあれだけ緊張していたから、かえってアナウンスが耳に入っていなかったかもしれないな…とも思いますが、お母さまのスキルを活かした、こんな共演もすてきですね。
お母さまは譜めくりすと?

親子で舞台に上がると言えば、わたし、一度だけコンクールで母に譜めくりを頼んだことがあります。
わたしの母は音楽は好きですし、練習もよく聞いているので曲の流れは把握しています。何より視力が驚異的に良いので、楽譜はそこまで速く読めなくても、とにかくよく見えるから大丈夫だろうと思って頼みました。
しかし譜めくりって弾くときとはまた違う緊張がありますよね。自分のミスを自分で回収できない仕事じゃないですか。それはそれは緊張したようで、出番終了後「(譜めくりすと)二度目はないかな…」と言われてしまいました。
いつもは本番のあととっても厳しい講評が待っているのですが、舞台に立つことの緊張に共感かつ同情と尊敬を得られて、そのときばっかりはとやかく言われなかったのを「いい気味だ」と思ったのはここだけのホンネ。まぁ、それ以降の本番では何事もなかったかのようにガンガン言われますけど。
*PR*
「進め! ヴァイオリンおけいこ道
あどゔぁんす」
おけいこ会員絶賛募集中
月額500円で、より深く本音を語った会員限定記事が読めます!
会員登録はこちら↓からどうぞ
最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)
- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20
- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18
- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30
- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07
- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28