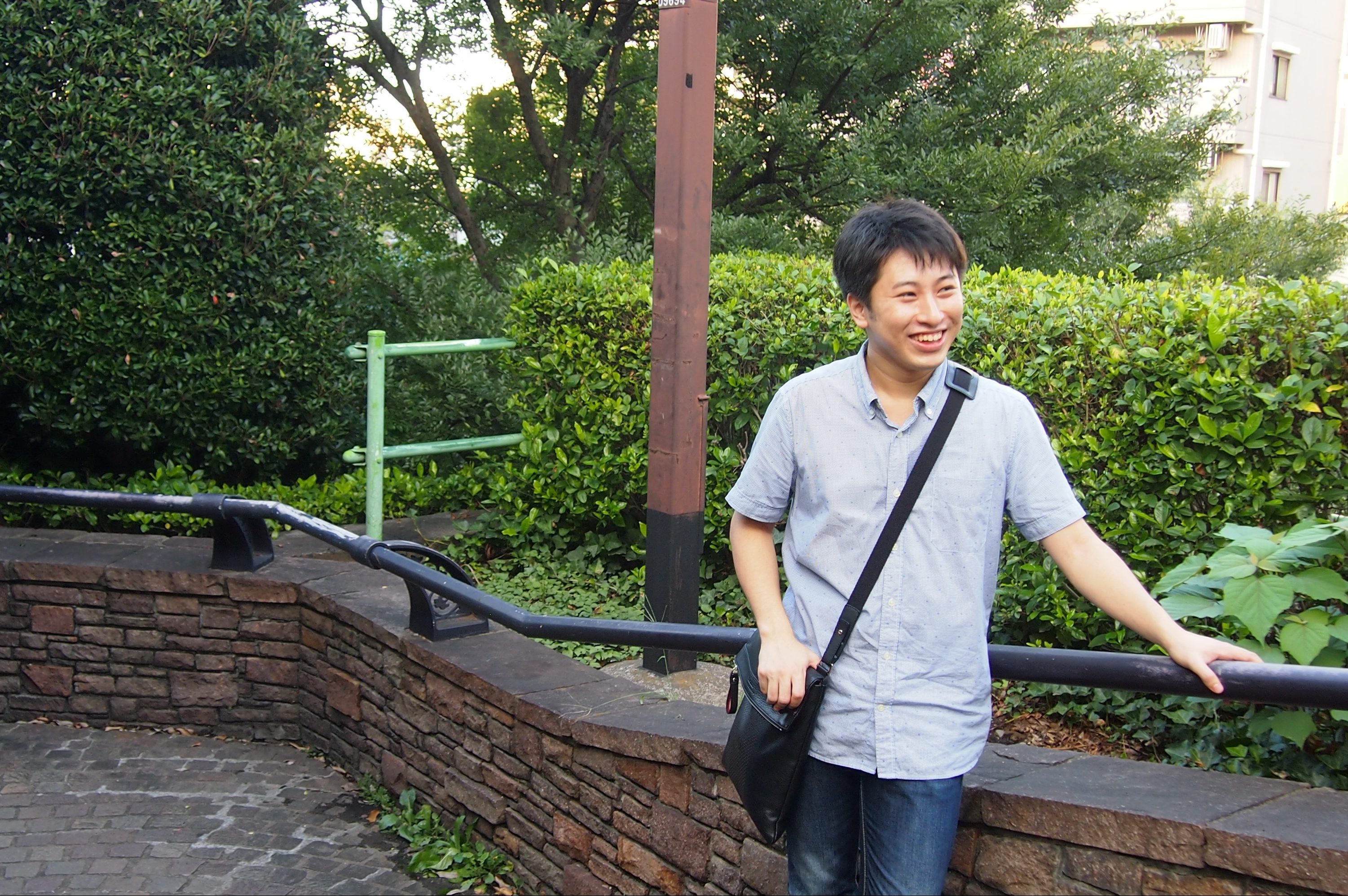ロンドンでヴィンテージに目覚める
―日頃からスリーピースのスーツやツイードのジャケットをお召しの渡邉さん。英国留学は先生の勧めで決められたわけですが、そういった服装はむしろイギリスの雰囲気によく合っていますよね。
ファッションには中学時代に興味を持ち始めて、高校3年生のときにテーラーに惹かれ始めました。大学に入って大阪のテーラー関係の人と知り合いになったり、出かけるときにはスーツを着ていったりしていました。
ロンドンに来てみたら、街並みが昔のまま保たれているので、トラディショナルな格好がすごく合うと思いました。なによりロンドナーはわりと自由で他者に干渉しません。だから僕も人の目を気にしなくなって、留学してからは毎日好きな格好をするようになりました。
そしてロンドンにはヴィンテージショップがたくさんあるので、見て回るのも大変楽しいです。放課後や休日になると折に触れ古着屋に顔を出していたところ、音楽院の1年目の終わりにとある靴に出会って、そこから僕はヴィンテージの靴の世界にのめり込んでいきました。

―今や “ヴィンテージシューズコレクター” としても知られ、靴に関する連載もお持ちの渡邉さんの靴キャリアは、ロンドンで始まったのですね!
出会った靴というのが、今はなき「オールドハット」というお店で見せてもらった1940年代の靴で、そのあまりの美しさに魅了されました。まず40年代の品物にもかかわらず誰も履いていない新品の靴で、そして現代の靴とは作りが違い、履いてみたら圧倒的に履き心地が良くて…そんな魅力を持っていながら、なんと学生でも手が届くお値段だったんです。あまりにすばらしい靴だったので購入して、今も気に入って履いています。

取材の日もその靴を履いていらっしゃいました
その半年後に、今度は音楽院の近くのセレクトショップでオーナーに靴の話を伺っていたところ、オーナーが僕の熱意に共感してくれて、その方のお気に入りだという靴を破格で譲ってくださったんです。それはご主人が若い頃、「トリッカーズ」というメーカーにご自分のためにオーダーしたものの、足を怪我して履けなくなってしまった一品で、けれどもあまりにすばらしい靴なのでずっと大切にとってあったそうです。そんな大切なものをいただいて恐縮する気持ちと、素敵な靴が手に入った喜びがありました。その後あれよあれよと出会いが続き、ヴィンテージシューズが持つそれぞれのストーリーに魅せられていくわけです。
―こういった靴が “学生でも手が届く値段” だということに驚きます。
日本だとヴィンテージシューズはとても高価なのですが、イギリスだと同じレベルのものがとてもお安く手に入ります。またイギリスには歴史が残っているのも最高です。
4足目に手に入れた靴は「ビスポーク」と言って、オーダーメイドで注文された靴でした。知り合いに譲っていただいたのですが、靴の中にオーダー番号とお店のラベルがあった上に、それが現存する靴屋だったので訪ねていったところ、帳簿にその靴の顧客情報が残っていたんです! その出来事に感激して、以来ヴィンテージシューズの中でもとくにビスポークシューズにコミットしてコレクションしています。今では靴そのもののみならず、靴屋の歴史やデザインの変遷にも興味があります。
―もっとも関心が高いのは何より “靴” なんですね! とはいえ、お洋服と帽子も相当こだわりがあるとお見受けしますが…?
帽子は友人がきっかけです。正直この服装で帽子をかぶるとコーディネートとして完成されすぎてしまう、やりすぎなのではないかと思って避けていたくらいでした。しかも自分には帽子は似合わないと思っていたんですよね。でも友人が帽子屋に勤めだしたので、付き合いでひとつ買ったら思いがけず良くて!
よく「帽子を日常的に取り入れられる人がうらやましい」と言われますが、帽子が似合わないというのは多くの場合思い込みなんです。まず帽子をかぶる自分の姿に見慣れていないこと、また新品の帽子はどうしても浮いて見えるので周りの人も見慣れない感じがするのが、似合わないと感じてしまう原因です。けれどその状態を少しだけ我慢すれば帽子が板についてきて、自分のシルエットに合うようになります。

服に関してはこのテイストが好きで数年前からずっと着ていましたけれど、ヴィンテージのものには目を向けていませんでした。あるときオールドハットさんに「ヴィンテージのオーバーコートがある」と声をかけてもらったので見に行くと、良い品でしたしコートはひとつほしかったので手に入れてみたものの、そのコートだけではヴィンテージにのめり込むほどの魅力が感じられませんでした。
しかし今年の春、本番衣装用に急きょ燕尾服が必要になっていろいろ調べて以来、服のほうでもヴィンテージがおもしろいと感じるようになりました。それまで古着は洗練されていないイメージでしたが、今では20世紀前半の縫製技術の高さやそこから生まれるシルエットの美しさに魅せられています。
音楽と、趣味と。

―その燕尾服が必要になった本番というのは、17年の6月にロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでおこなわれた英国王立音楽院の学生オーケストラによる公演のことですね。世界的指揮者であるセミヨン・ビシュコフ氏との共演で、また音楽院の演奏会がフェスティバル・ホールでおこなわれる機会は限られており、マエストロ自らの指定で男性は燕尾服を着用するよう求められました。
燕尾服をいちからオーダーするのはとても高額で、それでいて既製品ですと自分の体の中でもっとも大きい部分に合わせたサイズを購入することになるので、ダボついたりして美しいシルエットが得られません。そこでヴィンテージの燕尾服ならば体に合うものがお手ごろに見つかると思い至り、本番の2カ月前から探しました。
というのは、今でこそ大柄なイギリス人も、20世紀初頭は比較的小柄でしたので、今の日本人の華奢な体型には非常に都合良く着ることができます。加えて当時は燕尾服というのは社交の場で着るものですから、ダンスをすることを念頭に置いて作られているので運動性が高く、演奏もしやすいのです。
結果的に、デザインも着心地もすばらしい燕尾服を手に入れることができただけでなく、本番直前になって「燕尾服がない」と相談してきた友人の分まで見繕いました。また自分に手に入れた燕尾服は、元の持ち主が大地主だったことが発覚し、子孫の方が管理する広大なお屋敷にご招待いただいて貴重なお話を聞くことができました。この経験から燕尾服にもはまり、今では4着持っています。

―ヴィンテージの、特にビスポークの品々は、大切にされてきただけあってそれぞれが奥深いエピソードを持っていますね。燕尾服を通して音楽と趣味が融合したのはとても興味深いお話です。最後に、渡邉さんの今後の夢をうかがいたいです。
コントラバス奏者としては、やはりオーケストラに入って演奏したいという思いがあります。これは冗談ではありますが、オーケストラに入れば燕尾服を着て演奏する機会もたくさん持つことができます(笑)。
そしてせっかくこんなに突き詰めてしまった趣味も、何らかの形にしたいとは思います。たとえば先ほども触れましたが、日本人は昔のイギリス人の服をちょうど良く着ることができるので、日本のみなさんにイギリスのヴィンテージクローズのよさを伝えたいというのは少し考えています。特に音楽家の方には、ぜひ20世紀前半のテールコート(燕尾服)の良さを体感していただきたいです。
取材当日のコーディネートについてうかがうと、黒い靴の年代に合わせたという1940年代の紺色のコートに、同じ色のヴィンテージのハットを合わせミニマルな印象に、さらにグレーのスーツと組み合わせることでグレーとネイビー、黒というスタンダードな3色でまとめているのがポイントとのこと。そんなふうに語る渡邉さんを見ていると、現代のイギリス人よりも英国紳士らしいとすら感じました。また、その落ち着いた雰囲気とは裏腹に、コントラバスのこと、靴のこと、燕尾服のことを熱く語ってくださったのも印象的でした。
音楽とは、ある意味では常に歴史に思いを馳せ、その曲の裏側にある物語にアプローチをしながら作り上げるものです。そう考えると、渡邉さんが音楽家でありながら、専門職並みに靴や服に隠されたストーリーにのめりこんでしまうのも、不思議ではないかもしれません。
最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)
- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20
- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18
- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30
- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07
- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28