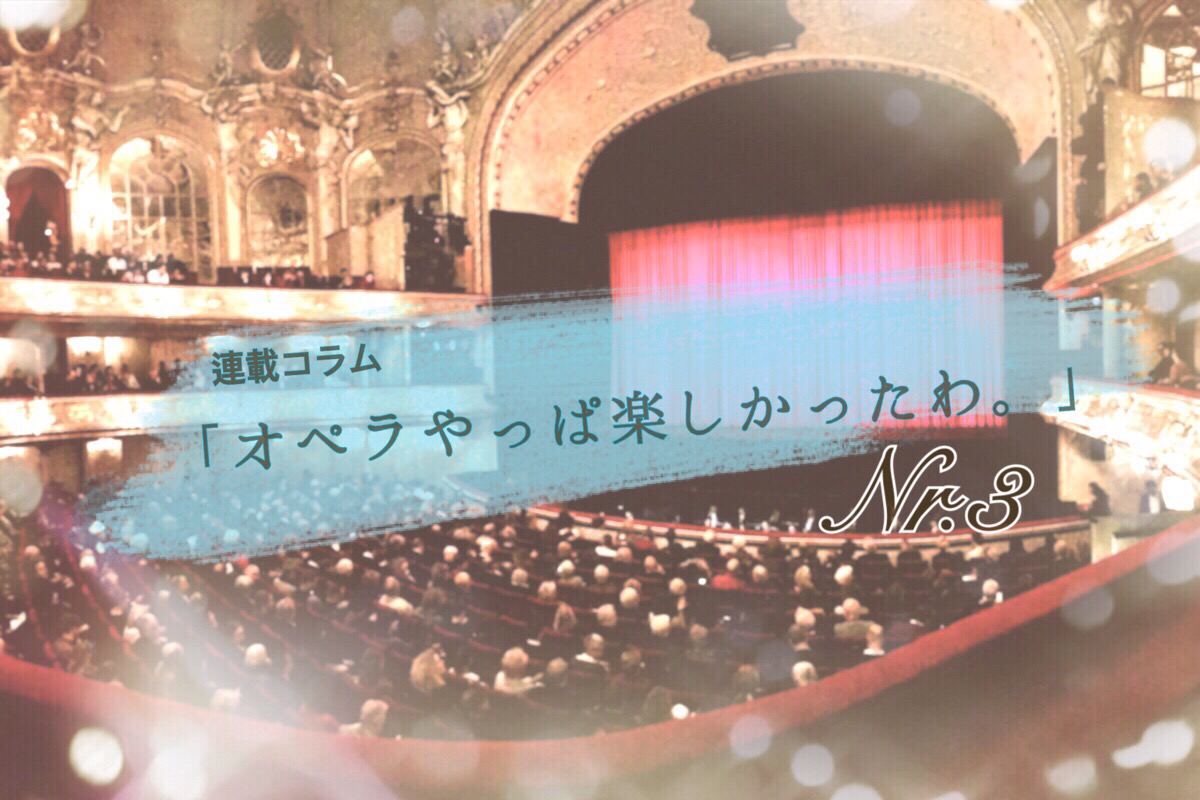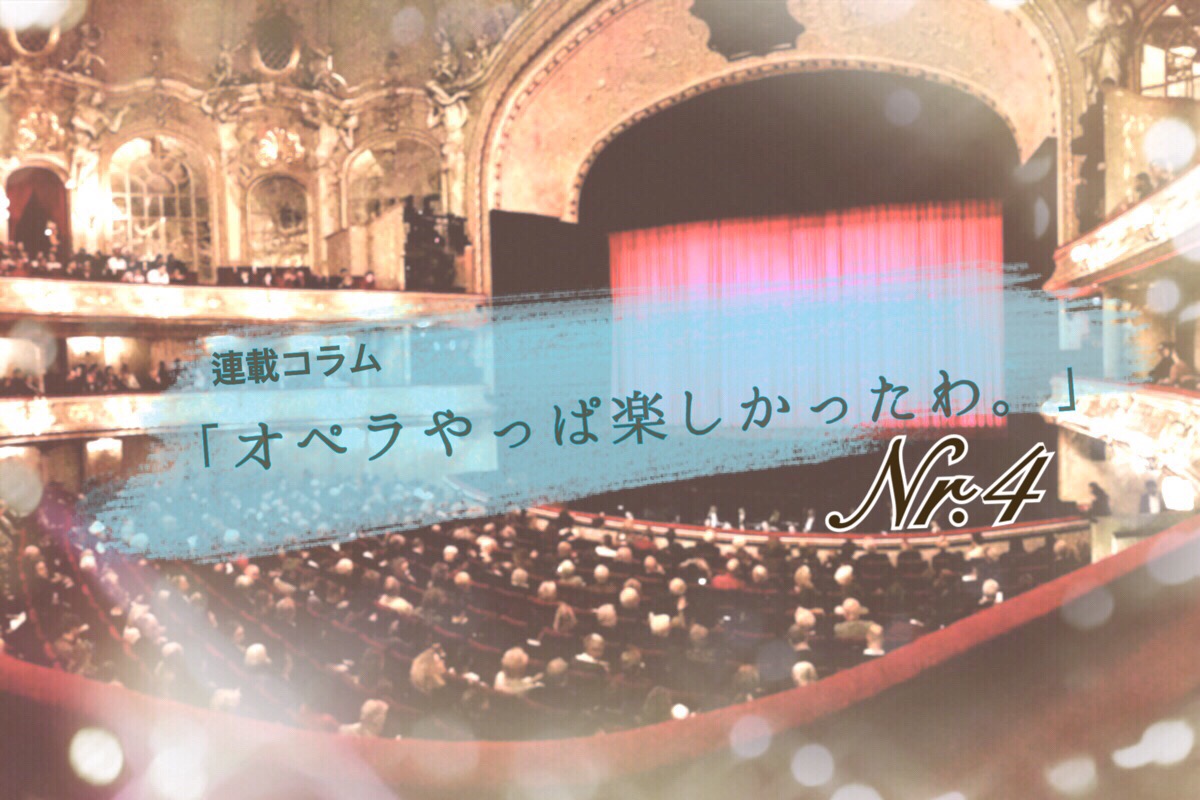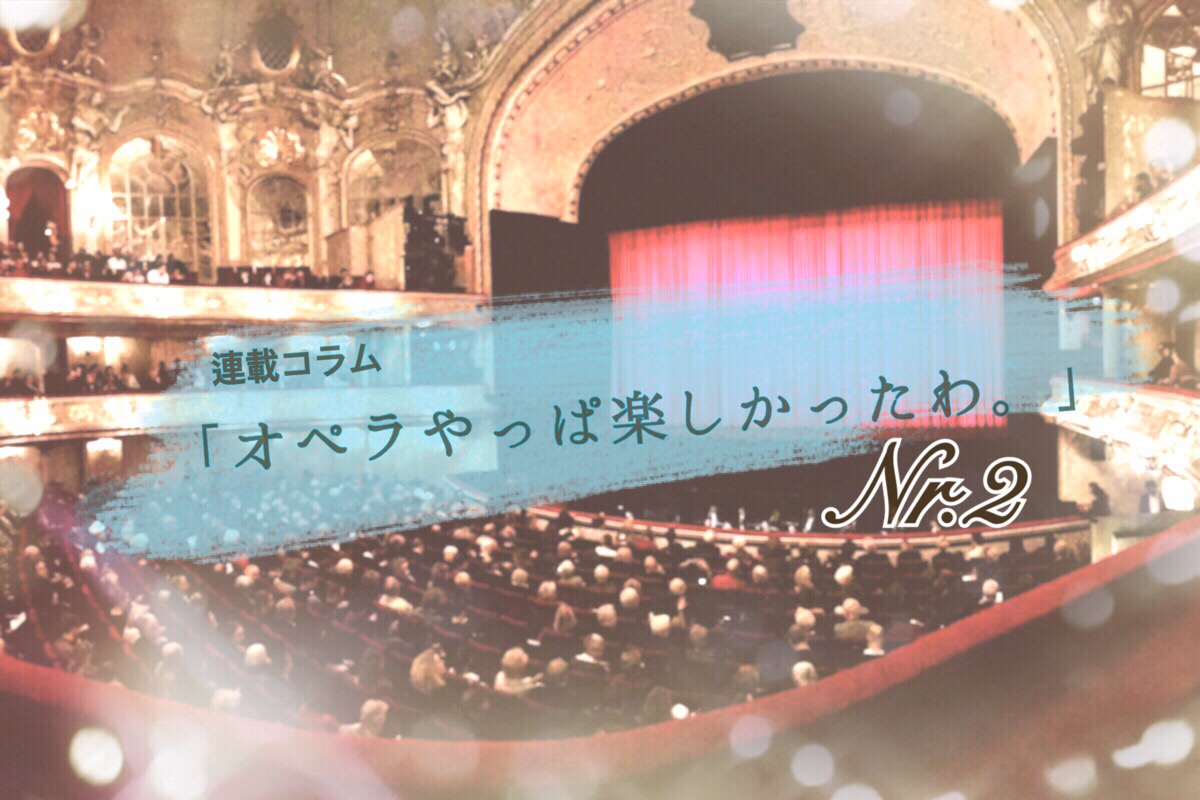本コラムは、声楽家・平山 里奈がベルリンで学ぶ中で、オペラの魅力を再発見していく様子を思うままにつづる連載作品です。
ドイツ最大級の劇場、ドイチェオーパー
このコラムの第 1 回で述べたように、私の住むベルリンには 3 つのオペラ劇場がある。先の 2 回はそのうちの「コーミッシェオーパー」での上演作品について書いたが、今回は 3 つの劇場の中で最大規模の「ドイチェオーパー」における、同じくモーツァルトの『コジ・ファン・トゥッテ』についてつづりたいと思う。
このドイチェオーパーは収容人数 1865 人とベルリンで最も大きく、ドイツ全土では 2 番目に大きな劇場である。海外から有名な歌い手が呼ばれ出演する頻度も高い。雰囲気もカジュアルなコーミッシェオーパーとは異なり、“ラグジュアリー”といった感じ。幕間にゼクト(ドイツ語でスパークリングワインのこと)なんぞを飲んでみれば、もう鼻持ちならない優雅さを身にまとえる。
しかし雰囲気とは、とても大事なものだ。オペラを観る上で、その観劇自体を楽しむのはもちろんだが、劇場に向かう前に自宅でどんな服を着ていくか考えるときから、オペラ観劇は始まっているように思う。行く劇場、見に行く演目に合わせてその日の服を選び、履きなれないヒールで劇場のロビーを闊歩(かっぽ)するのは、それだけで特別な気分が味わえるというものだ。
オペラの自由度

画像参照元:ドイチェオーパー公式サイト
『コジ・ファン・トゥッテ』はモーツァルト作品の中でも極めて有名な作品である上に、今日の日本での上演頻度が最も高いオペラ作品のひとつとも言えると思う。数多あるオペラ作品の中でこれほどまでに同じ演目が繰り返し上演されて、オペラファンであれば年に一度は観劇することになるだろうが、同じ曲、同じストーリーに飽き飽きしてこないのか。
答えはノーである。そのひとつにはオペラ作品の自由度が関係していると思う。オペラは楽曲こそ同じだが、指揮者次第で使用される楽譜の版が異なり、曲のテンポや表現が異なる。もちろん歌い手が違うことも、同じ楽曲を聴いてもまるで違う印象を与えうる。
加えて演出においては、それを拘束する指示が極めて少ないと言えるだろう。慣例や一般的解釈はあるにせよ、「必ずそれに倣う(ならう)ように」という指示はない。よって、公演毎に全く異なる作品を観ているような気持ちにさせてもらえるのである。
パリコレのような衣装
今回このドイチェオーパーの『コジ・ファン・トゥッテ』でひときわ印象に残ったのはその舞台衣装である。パリコレのようなモードな衣装。まるでファッションショーとオペラのコラボレーションを観ているようだ。こういった衣装の斬新さもオペラの見所のひとつであると私は思う。うっとり夢見るような美しいドレスや、時代に即した服装、はたまたとても現代的でアーティスティックな奇抜な衣装と、演出や衣装監督によって、オペラの雰囲気は本当にガラッと変わってしまうのだ。
『コジ・ファン・トゥッテ』第一幕の冒頭で、グリエルモとフェルランドが身に着けているスーツは、グスタフ・クリムトの絵を彷彿とさせるような幾何学模様で、ギラッギラしてなんともチャラそうだ。対してストーリーテラー的ポジションでもあるドン・アルフォンソは、黒ずくめに黄色いエナメルシューズ。この黒スーツに黄色いエナメルシューズというコーディネートは、今シーズンのドルトムント歌劇場で上演されていた『ファウスト』のメフィストフェレス役でも使用されていたが、流行なのだろうか。いかんせん私はファッションに疎い。
小間使いのデスピーナが、第一幕では魔女っ子のように黒くて裾が大きく広がったワンピースを着ていて、第二幕ではこれまた黒のエナメルボディースーツで登場したのも印象的だった。このようにして、オペラを観ることでファッションの兆候を推し量る事もできるのだ。一石二鳥どころではない。
オペラの鉄板ネタ
この『コジ・ファン・トゥッテ』にはいくつかの観客を笑わせる鉄板ネタが存在する。正直そのネタは、単体で現代の会話の中に盛り込んだり、私生活の中で使っても笑えない。ドッカーンとウケるようなクリティカルな笑いではない。しかしながら、本来ならば少し敷居が高いと感じる、お固いイメージなオペラの世界の中では、際立っておもしろく見えたりするものなのだ。
そのネタが出てくるのは第二幕フィナーレ、男性 2 人がなんとか女性陣の気を引くために毒薬を呑んだふりをする場面だ。どうしてそうなったのかについては、Wikipedia のあらすじを読めばすぐにわかる。この演出では毒薬の代わりに、なんかだかよくわからないその辺に生えているような草を食べていて、私はひとりでおなかを抱えて笑っていたのだが、さすがドイチェオーパー、お上品なお客樣方はそのことについては笑ってはいなかった。
“鉄板ネタ”はそのあとだ。服毒して苦しんでいることを強調するために「あぁ〜」と歌うのだが、これが非常に笑える。言葉にしてしまうとなんとおもしろくないのだろうか。笑いというものは元来、そのおもしろさを説明してしまうとたいしておもしろくなくなってしまう。しかし実際はとてもおもしろい。しかもよく見ている人なら「くるぞ、くるぞ!」と内心この一声を待ちわびていることだろう。待ち構えて、笑うのだ。
そして医師に変装した小間使いのデスピーナが電気ショックをかけてその毒を治療するのだが、電気にしびれる歌い手の演技がこれまた笑える。痺れている歌い手たちは、この演技、激しく体力を奪われると思われる。今回はかなり激しかった。あれは疲れる。痺れ芸に対する熱い歌い手の熱意をかいま見た。プロはどこまでも本気だ。
おもしろさとのバランス感覚

画像参照元:ドイチェオーパー公式サイト
オペラは楽しむものだ。それが喜歌劇であればなおのこと、そこにはおおいに笑う自由がある。そして演出家や演奏家たちも、その自由を観客が存分に味わえるように全力を尽くすのだ。『コジ・ファン・トゥッテ』に於いていえば、その笑いの部分と、シリアスな場面のバランスが見所のひとつであると思う。笑いを取ったあとに、緩んだ雰囲気をぴりっと締め上げて、物語の進行に緩急を付けていく。すばらしいことに、音楽も物語の内容に合わせて、緩急がしっかりと表現されているのだ。
しかし多く上演される分、観客も「あー、今回はこういうタイプの演出ね?」などと考えがち。予定調和をどのように崩して楽しませてくれようとしているのか、新鮮であることは刺激的であり、刺激的であることは楽しさを生む。観客は今日も今日とて、どんな新鮮さを味わえるのかとわくわくしながら、劇場に向かうのだろう。
輪湖 里奈
最新記事 by 輪湖 里奈 (全て見る)
- 「オペラやっぱ楽しかったわ。」Nr.11 - 17.11.28
- 輪湖里奈のドイツ留学後記その2 〜留学への決心と運命の出会い - 17.10.07
- 「オペラやっぱ楽しかったわ。」Nr.10 - 17.09.11
- 輪湖里奈のドイツ留学後記その1 〜渡航の決心から実現までの葛藤 - 17.08.22
- 「オペラやっぱ楽しかったわ。」Nr.9 - 17.07.28